【コツ】牛刀の研ぎ方は?両刃片刃で違う?角度やベタ研ぎ/おすすめの砥石まで解説!

牛刀は料理の中心となる万能包丁。しかし、最近「切れ味が落ちた?」と感じながらも、研ぎ方が分からず放置してしまっている人は意外と多いものです。
特に牛刀には基本の両刃だけでなく、片刃仕様の「和牛刀」も存在するため、利き手や角度を誤ると余計に切れ味が悪化したり、刃こぼれを招くことも。今回は、牛刀の基礎知識から、両刃/片刃ごとの研ぎ方の違い、正しい角度、ベタ研ぎのコツまで丁寧に解説します。
あわせて、初心者でも扱いやすい砥石の選び方やおすすめも紹介。牛刀の研ぎ直しは難しそうに見えますが、要点やコツさえ押さえれば誰でも切れ味を復活させることができます。今日から正しいメンテナンスを身につけて、料理をもっと快適に楽しみましょう。
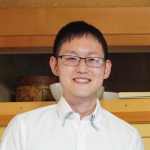
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

【基礎知識】牛刀とは?片刃タイプと両刃タイプが存在する?
牛刀(ぎゅうとう)は元々は西洋由来の洋包丁で、日本では肉はもちろん、野菜や魚など幅広い調理に使える万能包丁として広く普及しています。刃は細長く、引き切りが得意。自宅でのメイン包丁としても最も選ばれている種類です。
そして、牛刀の刃は基本的には両刃。左右均等に刃が付いているため、真っ直ぐ切り進めやすく、利き手を問わず扱いやすいというメリットがあります。
一方、日本の職人が和包丁の技術を取り入れて製作する場合、例外的に片刃の牛刀(=和牛刀)と呼ばれるタイプが存在します。こちらは片側のみ鋭い角度で研がれており、より鋭い切り口と高いコントロール性が得られる反面、利き手が限定され、研ぎには知識が必要とされます。
要するに片刃、両刃タイプ牛刀それぞれのすみ分けは以下の通りです。
- 片刃タイプの牛刀:専門性が高く、プロ向け(右利き用/左利き用が分かれる)
- 両刃タイプの牛刀:一般的で扱いやすい(初心者〜全般)
そして、詳しくは後述しますが研ぎ直しの際にはどちらかのタイプによって方法や気を付けることが変わってきますのでまず自分の牛刀がどちらかを確認することが大切です。
【難しい】薄刃包丁/和包丁の研ぎ方!片刃包丁はシャープナーより砥石を使うべき?

両刃牛刀の研ぎ方の基本手順
それでは、まずは両刃牛刀の研ぎ方についての基本手順を解説します。結論、それは以下の通り。
- 砥石をセットし、刃を手前に向ける
- 刃元〜切っ先まで数cmずつ小刻みに研ぐ
- 刃先にバリ(削りカスのめくれ)が出るまで研ぐ
- 裏面も同じ回数・同じ角度で研ぐ
- 仕上げは軽い力で数回、刃先を整える
それぞれ手順ごとに詳しく確認していきましょう。
両刃牛刀の研ぎ方①:砥石を安定させ、刃を手前に向けてセットする
研ぎの失敗は、実はここで決まります。両刃牛刀は左右の刃を均等に研ぐ必要があるため、まずは砥石自体がしっかり安定していることが大前提。濡れタオルや滑り止めシートを敷いて、絶対に動かない状態を作ります。刃は手前に向けることで、刃先の角度を目視しながらコントロールしやすくなります。
持ち手側(刃元)から始めると、重心が安定し、刃のカーブに合わせて研ぎ面を段階的に作ることが可能。家庭包丁は使用頻度や切る食材によって摩耗が偏りがちですが、この初期ポジションを整えることで、左右差を防ぎ、まっすぐ切れる両刃の本来の性能に近づける下準備になります。
両刃牛刀の研ぎ方②:刃元〜切っ先まで数cmずつ小刻みに研ぐ
両刃牛刀は刃先から背側へかけてなだらかに面が続く構造のため、研ぐ範囲を細かく分け、刃のカーブに沿って砥石へ当てていきます。このとき、角度の目安は約15°前後。角度のブレ=切れ味のムラとなり、切ると左右どちらかに曲がる原因になります。
力は押す方向にだけかけ、戻す際は力を抜くことで、砥石面の均しも同時に行え、金属疲労を抑えた優しい研ぎが可能に。滑らかに刃が走る位置を見つけたら、その角度を身体で覚えて維持し続けることが重要です。ここが最も習熟度が現れる工程とも言えます。
両刃牛刀の研ぎ方③:刃先にバリ(削りカスのめくれ)が出るまで研ぐ
研ぎ進めると、刃先の裏側に金属のめくれ=バリが発生します。これは刃先まで研ぎが届いた確かな証拠。特に両刃は刃幅全体に均一な刃を付けることが必要で、部分的にバリが出ない場合は角度が寝すぎていたり、力のかけ方に偏りがあるサインです。
硬い鋼材(ハイカーボン系)ではバリが出にくい場合もあるため、光に刃先を当てて輝きが残っていないか、爪に軽く当てて滑らないか、といった複数の視点でチェックするのが安心。焦って次の工程に進むと切れ味が復活せず、無駄に削ることにもつながります。
【仕上げ砥石】包丁研ぎでかえりが出ない理由!ステンレスだからわからない?

両刃牛刀の研ぎ方④:裏面も同じ回数・同じ角度で研ぐ
両刃牛刀は、左右の刃の付き方が均一であることで、真っ直ぐに切り進められます。そのため、表面が終わったら裏面も同じ角度・同じ回数で丁寧に研ぐことが必須。
面の形状が非対称になると、牛刀の最大の強みである引き切り性能が下がり、切るたびに刃が曲がったり、余計な力が必要になってしまいます。また、刃の中心が偏ると研ぎ減りが早くなり、寿命を縮める原因にも。
プロは癖のない中庸の刃を理想としますが、それを守る鍵がこのバランス維持。片刃とは異なる両刃ならではのルールとして押さえておきましょう。
両刃牛刀の研ぎ方⑤:仕上げは軽い力で数回、刃先を整える
最後の工程では、これまでしっかり出したバリを整えて消すことに集中します。強い力のまま研ぎ続けると刃先が不安定になり、せっかくの鋭さが台無しに。軽いストロークで表裏を数回ずつ、刃先の通りを確認しながら揃えます。
その後、新聞紙やまな板の木面で刃裏を軽く滑らせ、バリだけを取り除けば完了。バリを残してしまうと、すぐに切れ味が落ちたり、食材が毛羽立ったりする原因になるのでここは念入りに。
仕上げの一手間が、引っかかりなくスッと切れる両刃牛刀の本領を引き出せるかどうかの鍵となります。
片刃牛刀の研ぎ方についての注意点(右利き用)
片刃牛刀の研ぎ方についてですが、両刃タイプの場合と異なり主に以下3点について注意する必要があります。
- 主刃側(右側)をしっかり研ぐ
- 裏面(左側)は平面を保ちながらバリ取り+面直しだけ
こちらもそれぞれ見ていきましょう。
片刃牛刀の研ぎ方に注意点①:主刃側(右側)をしっかり研ぐ
片刃牛刀の場合、鋭い切れ味の源となる主刃側(右側)の研ぎが最も重要です。目安角度は15°弱の鋭め。刃元から切っ先まで細かく分け、刃のカーブに沿わせながら砥石へ均一に当てていきます。
力を入れるのは押し方向だけにし、戻す際は力を抜くことで、砥石面を荒らさず滑らかに研ぎ進められます。研ぎ中は刃先にバリが連続して出ているかを必ず確認。部分的にバリが出ない場合は角度が寝すぎている、または力の偏りが起きている証拠。
主刃側の仕上がりで切断時のスムーズさが決まるため、焦らず丁寧に刃先まで研ぎを通すことが、片刃牛刀の特性である鋭い引き切り性能を引き出す鍵となります。
片刃牛刀の研ぎ方の注意点②:裏面(左側)は平面を保ちながらバリ取り+面直しだけ
片刃牛刀の裏面(左側)は、切り口を真っ直ぐに導くためのフラットな道の役割を持ちます。この面を削りすぎたり、角度をつけて研いでしまうと、片刃特有の切り進みの良さが損なわれ、切り曲がりや刃こぼれの原因になりかねません。
そのため、裏は基本的に角度ゼロで砥石へ面一(つらいち)に当て、バリを軽く落とす程度に数回だけ優しく研ぐのが正解。力をかけずに滑らせるように動かし、裏面の歪みを防ぎます。
主刃側で生まれた鋭い切れ味を支え、食材の抜けを良くするのが裏の役割。裏を削るのではなく整えるという意識を徹底することが、片刃牛刀を長く良い状態で保つコツですよ。
【砥石】菜切り包丁の研ぎ方は間違えやすい?片刃/両刃タイプによる角度の違いを解説

【応用編】牛刀の ベタ研ぎとは?切れ味と刃持ちが変わる重要ポイント
牛刀の研ぎで意外と見落とされるのが、刃先だけでなく刃の面全体を整えるベタ研ぎ(平研ぎ)の重要性。
ベタ研ぎとは、刃元から刃先までを砥石にしっかり密着させ、刃の面を均一に整える研ぎ方です。これにより、刃体(刃先以外の側面)の厚みが均一になり、食材への入り込みが軽くなる=切れ味が長持ちしやすくなります。
特に、両刃牛刀は使用を重ねると徐々に刃の根本が厚みを帯び、研ぎ直しても「なんだか切れ味が戻らない」という状態に陥りがち。これは、刃先より上の部分(肩)が太ってしまい、食材に当たる抵抗が増えていることが原因です。
ベタ研ぎを取り入れることで、この肩の厚みを適切に落とし、牛刀本来の抜けの良さである、真っ直ぐスッと入る切れ味を取り戻せます。
ただし削りすぎは刃の寿命を縮めるため、日常の研ぎでは角度研ぎを中心に、時折ベタ研ぎを織り交ぜるのが理想的です。刃のカーブに合わせて砥石へ寝かせ、全体をなでるように数回。定期的なベタ研ぎが、牛刀を長く快適に使う秘訣ですよ。
また、使っている牛刀について、以下症状に該当する時は刃先ではなく刃体の厚みに問題がある可能性が高いため、ベタ研ぎを検討するべき頃合いと言えるでしょう。
- 研いでも切れ味が戻らない
- 野菜や肉の皮で止まる
- 食材に引っかかり、押し切りが多くなる
- 切り口がボソボソする
【豆知識】牛刀の研ぎ角度を簡単に確認する方法
ここまで述べてきたように、片刃、両刃タイプともに牛刀を研ぐ際に重要なのは研ぎ角度の維持です。
しかし、専門家でもなければ感覚だけで正確に角度をキープするのは困難。そこで、家庭でも簡単に使える 3つの角度確認方法 を豆知識として3つほど紹介しておきます。
方法①:コイン法(最も簡単)
砥石と刃の間にコインを1~2枚挟んだ高さが、牛刀研ぎの基準角度である約15°に相当。実際に挟んでみたり、コインを置いた高さを感覚として覚えることで、研ぎ中の角度ブレを防止できます。
初心者にありがちな“寝かせすぎ”を防げるうえ、左右両面で同じ高さを再現しやすく、バランスの良い両刃の研ぎ上がりを実現できます。
方法②:ペン法(刃先まで研げているか視覚的に判断)
刃先近くに油性ペンで薄く線を引き、そのインクが研ぎ途中で均等に消えるかチェックする方法です。
刃先に光が残ったりインクが消えない部分は、角度が寝すぎて砥石に当たっていない証拠。研ぎムラや切れ味の低下を防ぐ上で非常に役立ち、短時間でも改善効果が出やすいテクニックです。
方法③:面の当たり具合で判断(慣れるほど精度が上がる)
刃体(ベベル)全体が砥石に「ピタッ」と密着し、滑らかに砥石を走る位置が正しい角度です。
ザラザラと不規則な音や引っかかりがある場合は角度が浮いているサイン。慣れるほど音と感触で角度が掴めるようになり、研ぎにスピードと精度が出ます。両刃の左右バランスを維持しながら角度を合わせられる上級者向けの感覚です。
牛刀研ぎにおすすめの砥石|番手の選び方と最適な組み合わせ
家庭で牛刀を研ぐ場合、まず揃えたいのは中砥石です。
特に#1000前後の番手は扱いやすく、切れ味回復には万能。1枚持っておけば、日常的なメンテナンスの中心として十分役立ちます。刃欠けなど大きなダメージがある時のみ#320〜#400の荒砥石を使用しますが、削りすぎると刃が減りすぎてしまうため、初心者は慎重に使うのが鉄則。
逆に刺身など繊細な引き切りを求める場合は、#3000以上の仕上げ砥石が効果的で、刃先に光沢が出て食材の抜けが良くなります。つまり、まずは中砥石1枚を基礎として、必要に応じて荒砥・仕上げ砥を追加していくのが失敗しない砥石選びのコツです。
また、砥石の材質にも違いがあります。多くの砥石はセラミック製で、水に浸ければしなやかな研ぎ感が得られ、仕上がりも良好。一方、ダイヤモンド砥石は変形しにくく、砥石面の平坦性を維持しやすい特徴があります。特に牛刀は刃幅が広いため、ベタ研ぎを続けていると砥石の平面が崩れやすいもの。
そこで、ダイヤ砥石で土台となる形を整えつつ、中砥石で最終的な切れ味を引き出す組み合わせが非常に理にかなっていると言えます。初心者でも角度が安定しやすいため、効率良く研ぎ上げることができますよ。
なお、砥石の種類や番手のすみ分けについて網羅的に知りたい方は以下別記事もご参考下さい。
【粗さ】砥石の種類5選!番手がわからない時の対処法まで徹底解説

初心者でもプロ級の切れ味に|EDGBLACKなら角度迷いゼロで研げる
牛刀を正しく研ぐためには、角度の維持や両刃・片刃の違いを正しく理解しなければいけません。しかし、実際には「角度が安定しない」「刃先だけ当たってしまう」「左右のバランスが崩れる」といった失敗も多く、研いだつもりが切れ味を悪化させてしまうケースも少なくありません。
そこでおすすめしたいのが我々 EDGBLACK(エッジブラック) の包丁研ぎツールです。Flexモデルは角度調整ガイドが付いており、刃を固定するだけで常に最適な角度をキープ。電動タイプは一定方向へ軽く引くだけで切れ味が復活します。
特に両刃牛刀では左右均等の角度が重要ですが、その難易度の高い部分をツールが補ってくれるため、研ぎ慣れていない家庭でも安心して使えるのが魅力です。
「砥石の知識がまだ不安」「失敗したくない」という方にとって、EDGBLACKはプロの結果を家庭で再現できる実用的な選択肢と言えるでしょう。
【コツ】牛刀の研ぎ方は?両刃片刃で違う?:まとめ
牛刀は両刃が基本ですが、和包丁技術を取り入れた片刃仕様も存在します。そのため自分の牛刀がどちらなのかをまず確認することが、正しい研ぎの第一歩。両刃は左右均等の角度を保つことで真っ直ぐ切れ、片刃は主刃側を研ぎ、裏は平面を整えるだけという構造上の違いを意識する必要があります。
また、刃先だけでなく刃体全体を整えるベタ研ぎを取り入れることで、食材への入り込みが驚くほど軽くなります。砥石は中砥石(#1000前後)を基本に、必要に応じて荒砥・仕上げ砥を追加すれば十分です。
牛刀を研ぐ際の角度のキープはコイン法やペン法が有効で、初心者でも再現しやすい手法です。難しさがある一方で、正しく研げれば切れ味は確実に蘇り、料理の楽しさが大きく変わるはずです。
その際に是非、牛刀研ぎを手軽にかつプロ級の仕上がりにできる我々EDGBLACKという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /










コメント