【5選】天然砥石の見分け方!人造砥石との違いやメリット・デメリットまで徹底解説

刃物を研ぐうえで重要な道具である砥石ですが、「見た目では判別が難しい」「高価な天然砥石を買って失敗したくない」といった不安を抱える人も多いでしょう。
特に初心者にとっては、層の模様や手触り、水の吸い込み具合といった見分け方のポイントが分からず、選び方でつまずいてしまうケースも多いはず。
そこで今回は「天然砥石の見分け方」と「人工砥石との違い、それぞれのメリット・デメリット」について徹底解説します。
本記事では、実際に購入前にチェックすべき具体的な判断基準や、初めての一本におすすめの砥石も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
>>【10選】天然砥石の種類まとめ!最高級品から産地ごとの特徴まで徹底解説

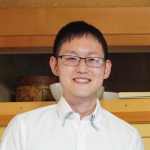
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

天然砥石の見分け方
天然砥石は、人工砥石では再現できない研ぎ味や仕上がりの美しさから、今もなお多くの職人や愛好家に選ばれ続けています。
しかし、その価値の高さから人工砥石を“天然風”に仕上げた商品も多く流通しており、本物を見極める目が必要です。
まずは、天然砥石の見分け方を5つに分けて解説していきますね。
- 表面に自然な層や模様、色のムラがあるかを見る
- 手触りに粒子のばらつきや自然なザラつきがあるか確認する
- 持ったときに人工砥石より重く密度感があるか確かめる
- 水を垂らしたときにじわっと吸い込み色が変わるか観察する
- 価格が高く、信頼できる専門店や産地から販売されているか確認する
順番に見ていきましょう。
見分け方①:表面の模様や層の自然さを確認する
天然砥石は地層から採掘されるため、表面には自然が作り出した層や色のムラ、鉱物が混ざり合った複雑な模様が現れます。人工砥石は工場で作られるため、粒度が均一で表面が滑らかになりやすく、模様もほとんどありません。
特に京都本山系の砥石では「巣板」「浅黄」「戸前」などの層が地層の年輪のように出ることがあり、それが本物の証とされています。また、自然な砥石は一枚ごとに表情が異なり、同じ名称でも色味や模様がまったく違うことが多いです。
人工砥石のように“どれも同じ”ではなく、一点物としての個性があることが見分けの大きなポイントになります。表面に直線的なパターンや均一な色が続く場合は人工の可能性が高いため注意しましょう。
見分け方②:手触りと粒子のばらつきを感じ取る
天然砥石は砥粒の大きさや分布が自然任せであるため、指で撫でたときに粒子の細かさが部分ごとにわずかに異なります。
人工砥石は粒子が規格化されているため、どこを触っても均一でサラサラした質感ですが、天然砥石には独特の“ざらつき”や“引っかかり”があります。これは鉱物が複雑に混ざり合っている証拠で、研ぎ味にも反映され、包丁の刃先に自然な丸みや鋭さを与える要因です。
特に硬口の仕上げ砥では指先にしっかりとした抵抗感があり、軟口の砥石ではしっとりとした滑らかさが感じられるなど、触感が石ごとに異なる点も特徴です。購入前に実際に触れられる機会があれば、必ず表面の質感を確認し、均質すぎないかどうかをチェックすることが大切です。
見分け方③:重さと密度感を確かめる
天然砥石は自然の鉱物が長い時間をかけて圧縮されてできたため、見た目以上にずっしりとした重みがあります。
人工砥石は素材が均一なため比較的軽く感じることが多く、手に取った瞬間に違いがわかるほど。また、同じ大きさでも天然砥石の方が密度が高く、持ち上げたときに「詰まっているような感覚」があります。
この密度は研磨性能にも直結し、刃物のエッジをより細かく仕上げる効果があります。逆に、見た目の大きさに対して軽すぎる砥石は人工である可能性が高いと判断できます。
購入前に必ず重量感をチェックし、天然砥石特有の“鉱物の詰まり”を感じられるかどうかを確かめると安心です。特に大判の仕上げ砥ほどその差は顕著に表れます。
見分け方④:水を垂らしたときの吸い込み方を見る
天然砥石は内部に微細な空隙があり、水をかけると表面からじわっと吸い込む特徴があります。これに対して人工砥石は密度が均一なため、水が表面に残りやすく、なかなか浸透しません。
さらに、天然砥石の場合は吸水とともに表面の色が濃く変化し、研ぎ泥が出やすい性質を持っています。この泥は研ぎの仕上がりにも大きく関わり、刃先を滑らかに整える役割を果たします。
吸水性が低い砥石や水が玉のように弾かれるものは人工である可能性が高いため注意が必要です。実際に使用する前に、表面に数滴の水を垂らして吸い込み方を観察するだけでも判別の精度が高まるでしょう。
天然砥石ならではの「呼吸するような吸水性」は、人工砥石にはない大きな特徴のひとつです。
見分け方⑤:価格と販売元の信頼性を確認する
天然砥石は採掘量が限られ、品質の高いものは非常に希少なため、価格が人工砥石よりも高額になるのが一般的です。
京都の本山砥や中山砥などは、状態やサイズによって数万円から十数万円することも。そのため、異常に安価な「天然砥石」には注意が必要です。また、信頼できる砥石専門店や伝統産地から販売されているかどうかも重要な判断材料です。
採掘地や層の情報、石質の説明が明確に記載されているものほど信頼性が高いといえます。特にネット通販などで購入する場合は、販売元の評価や取り扱い実績を必ず確認し、曖昧な表記の商品は避けたほうが安全です。
>【比較】砥石とシャープナーの違いは?7項目からどっちがいいのかを徹底比較

砥石は天然だから良いわけではない
「砥石は天然であれば必ず優れている」という考え方は誤解です。
確かに天然砥石は、刃先の質感を細やかに仕上げる力や、職人が好む独特の研ぎ味といった魅力があります。しかし、それは必ずしもすべての用途や人にとって最適という意味ではありません。
むしろ、現代の包丁や工具の多くは工業製法により素材や焼き入れが進化しており、それに合わせた人工砥石の方が効率的で実用的な場面が多いのです。
人工砥石はJIS規格で粒度や硬度が統一されており、同じ番手なら再現性の高い研ぎが可能。例えば、家庭用包丁の研ぎ直しにおいては#1000前後の中砥が最も使用頻度が高いとされており、人工砥石ではこの粒度が安定して供給されています。
一方、天然砥石は同じ産地・層でも個体差が大きく、研ぎ味や仕上がりが異なるため、扱いには経験が必要です。特に初心者がいきなり天然砥石を使うと、角度や圧力が安定せず、かえって刃先を痛めてしまうケースもあります。
重要なのは、素材そのものではなく、用途と使う人の技量に合っているかで決まるという点です。プロの研ぎ師が日本刀や高級和包丁を仕上げるなら天然砥石の特性が活きますが、家庭で週に数回包丁を研ぐ程度なら人工砥石の方が扱いやすく、結果も安定しますよ。
>>【失敗事例】包丁を研いだら切れなくなった?!研ぎすぎ原因?下手である理由を徹底解説

天然砥石のメリット・デメリット
次に、天然砥石のメリット・デメリットを見ていきましょう。
天然砥石のメリット
- 刃先の仕上がりが滑らかで切れ味が長持ちしやすい
- 砥石ごとに異なる研ぎ味があり、仕上がりに独自の風合いが出せる
- 鏡面仕上げや高級刃物の最終研ぎなど精密な研磨に向いている
天然砥石が今なお多くの職人や愛好家に支持されている最大の理由は、人工砥石では再現できない仕上がりの美しさと切れ味の質にあります。
まず注目すべきは、刃先の仕上がりが非常に滑らかになる点です。天然砥石は鉱物が複雑に混ざり合い、粒度が自然に変化しているため、刃物のエッジを極めて繊細に整えることができます。
その結果、包丁や鉋の切れ味が長持ちしやすく、研ぎ直しの頻度も減る傾向があります。特に料理包丁の場合、研ぎ後の切断抵抗が減少し、野菜や肉の断面がきれいに仕上がるため、調理の質そのものを高められる点が大きな魅力です。
さらに、天然砥石ならではのメリットとして「研ぎ味の個性」があります。
同じ産地や層の砥石でも一枚ごとに性質が異なり、刃への当たり方や研磨の進行具合が微妙に変わります。この違いが仕上がりの風合いに独自の表情を与え、人工砥石では得られない“刃物との対話”のような感覚を味わえるのです。
例えば、中山砥や奥殿砥といった高級仕上げ砥は、微細な粒子が金属表面の凹凸を自然に整え、刃先にしなやかな強さと粘りを持たせます。こうした「一つとして同じものがない」個性こそが、職人が天然砥石を選ぶ理由と言えるでしょう。
また、天然砥石は鏡面仕上げや高級刃物の最終研ぎといった、精密な作業にも非常に向いています。
泥(スラリー)の出方や研磨圧の変化を繊細にコントロールできるため、人工砥石では到達できないレベルの仕上げを実現可能。特に日本刀や高級和包丁など、刃先だけでなく見た目の美しさも求められる分野では、天然砥石が欠かせません。
天然砥石のデメリット
- 個体差が大きく、同じ種類でも研ぎ味や仕上がりが一定しない
- 高価で入手しにくく、大判や高品質なものは数万円以上になる
- 吸水や泥出しなど扱いに手間がかかり、初心者には使いこなしが難しい
天然砥石には魅力が多い一方で、同じ呼び名でも一枚ごとに性格が違うデメリットがあります。
個体差は形成環境に由来し、硬さや砥粒の当たり方、泥の出方まで変わるため、狙った仕上がりを毎回再現するには学習が必須。銘や層が同じでも研ぎ味が一致しないことがあるため、替えを用意しても同等品として置き換えられない場面が出ます。
次のデメリットは、価格と入手性です。
品質の高い原石は産地や層の枯渇に影響されやすく、大判や均質な面を持つ個体は市場に出る量が限られます。需要に対して供給が少ない局面では、コンディションやサイズを妥協せざるを得ないこともあるでしょう。
さらに、扱いには時間と手間が必要です。
使用前の吸水で砥面の状態を整え、研ぎの途中は泥を意図的に育て、圧と水分量を刻々と調整する運用が必要です。
このプロセスは仕上がりを左右する反面、習熟が浅い段階では刃先を甘くしたりムラを生んだりと逆効果になりがち。面直しや乾燥管理を怠れば歪みや割れにつながり、せっかくの石が本来の力を発揮できません。
人工砥石のメリット・デメリット
次に、人工砥石のメリット・デメリットを見ていきましょう。
人工砥石のメリット
- 粒度が均一で仕上がりの再現性が高い
- 価格が比較的安く入手しやすい
- 水浸けや泥出しが不要で初心者でも扱いやすい
人工砥石最大のメリットは、扱いやすさと安定性です。
まず挙げられるのが粒度の均一性。人工砥石は工業的に製造されているため、砥粒の大きさが一定に揃えられており、同じ番手であればどの製品を使ってもほぼ同じ研ぎ味と仕上がりが得られます。
また、番手が明確に数値化されているため、刃の状態に合わせて粗砥・中砥・仕上げ砥を選びやすく、研ぎの工程設計もしやすいと言えるでしょう。
さらに、人工砥石はコスト面でも大きなメリットがあります。
天然砥石が希少性や産地によって数万円から十数万円に達するのに対し、人工砥石は量産が可能なため価格が安定しており、一般的な中砥であれば数千円台から購入できます。
全国のホームセンターやオンラインショップで入手しやすく、サイズや形状のバリエーションも豊富なため、自分の用途に合った一枚を選びやすいのも特徴です。
また、人工砥石は日常的なメンテナンスや使い方の面でも利便性が高いです。
多くの製品は吸水が不要で、水を軽くかけるだけですぐに使える「 splash & go 」タイプも多く、研ぎ前の準備時間がほとんどかかりません。天然砥石のように泥を出す工程や砥面管理に神経質になる必要がなく、平面出しも比較的簡単に行えます。
人工砥石のデメリット
- 天然砥石に比べて研ぎ味がやや硬く、仕上がりの風合いに深みが出にくい
- 高温での研磨や長時間の使用で摩耗や変形が起こりやすい
- 番手ごとに複数枚を使い分ける必要があり、研ぎ分けの手間が増える
人工砥石は扱いやすくコストパフォーマンスにも優れた道具ですが、使い方や目的によってはデメリットが存在します。
まず挙げられるのは、天然砥石と比べて研ぎ味がやや硬く、仕上がりの風合いに深みが出にくいという点です。人工砥石は均一な粒度を持つことで安定した研磨力を発揮しますが、その一方で、金属表面に自然な丸みや滑らかさを与える“微妙な当たり”が少なくなりがち。
特に和包丁や鉋といった繊細な刃物では、仕上がりがやや機械的に感じられることがあり、刃の粘りや切れ味の「伸び」にこだわる職人からは物足りなさを指摘されることもあります。
また、摩耗や変形が起こりやすい点も注意が必要です。
人工砥石は結合剤によって砥粒を固めて作られていますが、長時間の研磨や高温下での使用によって砥面が不均一になりやすく、特に中心部が凹む「くぼみ」が発生するケースがあります。
そのため、定期的な面直しやメンテナンスが欠かせず、使用頻度が高いほど手間とコストがかかる点は大きなデメリットといえるでしょう。
さらに、番手ごとに複数枚を使い分ける必要があることも、人工砥石特有の欠点です。
天然砥石のように一枚で幅広い番手帯をカバーすることが難しく、荒砥・中砥・仕上げ砥と段階的に用意しなければ十分な性能を発揮できません。
このように、人工砥石は、日常使いや趣味の範囲では問題ありませんが、仕上がりにこだわるプロの現場では、これらの性質を理解したうえで使い分けることが重要になるでしょう。
天然砥石の見分け方:まとめ
天然砥石は一見すると人工砥石との違いが分かりにくいものですが、層の模様や色のムラ、手触りのざらつき、水を吸い込む様子などを丁寧に観察すれば、ある程度の判別は可能です。
また、重量感や密度の高さも大きな手がかりとなり、信頼できる専門店から購入することが本物を手に入れる最も確実な方法といえるでしょう。とはいえ、天然砥石は個体差が大きく、品質のばらつきも避けられません。
そのため、最初の一本には扱いやすく安定した性能を持つ人工砥石を選ぶのも賢い選択です。中でも「EDGBLACK」のようなモデルは、シャープナー感覚で使えて手入れも簡単なうえ、研ぎ味も安定しており、初心者から上級者まで幅広く活用できます。
天然砥石の特徴を理解したうえで、用途に合わせた選び方を意識すれば、研ぎの質と満足度は一段と高まるでしょう。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /










コメント