【砥石】菜切り包丁の研ぎ方は間違えやすい?片刃/両刃タイプによる角度の違いを解説

一見シンプルな形をした菜切り包丁ですが、実は研ぎ方を間違えやすい包丁の一つ。
その大きな理由が、片刃タイプと両刃タイプで適切な研ぎ角度や手順が全く異なることにあります。構造の違いを理解せずに自己流で研いでしまうと、全然切れ味が戻らなかったり、刃先が丸くなってしまうといった失敗を招きがち。
さらに、近年は両刃タイプの菜切り包丁が増えているため、昔ながらの片刃を前提とした研ぎ方ではうまくいかないケースも多くなっています。
今回は、菜切り包丁の基本構造や片刃/両刃の違いを踏まえつつ、それぞれに適した研ぎ角度・研ぎ方・道具選び(シャープナー vs 砥石)について徹底解説。加えて、研ぎの失敗や角度調整の手間を減らしたい人向けにお得な情報も紹介しているので是非最後までご覧ください。
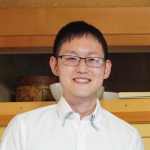
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

【基礎知識】菜切り包丁の定義や歴史変遷、和包丁との関係について
菜切り包丁(なきりぼうちょう)は、日本の伝統的な和包丁の一種で、野菜の調理に特化した包丁です。刃先が直線的で長方形に近い形状をしているのが特徴で、千切りやざく切り、皮むきなど、野菜を均一に切る作業で力を発揮します。
元来菜切り包丁は、和包丁の中でも「薄刃包丁(うすばぼうちょう)」の系統に属します。薄刃包丁はプロの料理人が野菜の桂剥きや飾り切りなど精密な作業に使う片刃構造の包丁で、菜切り包丁はその家庭用として江戸時代に広まったとされています。和包丁特有の片刃構造と鋭い切れ味によって、野菜の繊維を潰さずスパッと切ることができるのが菜切り包丁本来の特徴なのです。
しかし戦後になると、洋包丁(牛刀や三徳包丁)の普及や調理スタイルの多様化に伴い、両刃タイプの菜切り包丁が登場します。両刃は利き手を問わず使えるうえ、砥石研ぎが苦手な家庭でもメンテナンスしやすいため、急速に広まりました。
加えて最近では、市場に出回っている菜切り包丁の多くがステンレス製・両刃タイプで、シャープナーにも対応しやすい形状へと変化してきました。
このように、菜切り包丁は和包丁としての伝統的な片刃構造をルーツに持ちながらも、時代や家庭環境の変化に合わせて進化を遂げてきました。和包丁としての伝統的な菜切り包丁か、現代的な両刃包丁としての菜切り包丁かによって、研ぎ方の考え方も大きく変わってくるというわけです。
【重要】片刃と両刃の構造の違いを理解しよう
菜切り包丁を正しく研ぐためには、まず片刃と両刃の構造上の違いをきちんと押さえておく必要があります。見た目が似ていても、刃の断面構造や切れ味の性格は大きく異なります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
片刃構造(和包丁タイプ)の菜切り包丁

片刃包丁は、片面(右利き用では右側)のみに斜面(切刃)がついていて、裏面は平らな構造をしています。裏面には「裏スキ」と呼ばれるわずかな凹みがあり、これが切る際に刃をまっすぐ進ませ、野菜をスパッと割るように切断します。
この構造により、片刃包丁は非常に鋭い切れ味と優れた直進性を持ち、薄切りや桂剥きなど精密な作業に向いています。一方で、利き手が限定される(右用・左用が別々に存在)ことや、扱いに慣れが必要といった面もあります。
両刃構造(現代型・洋包丁寄り)の菜切り包丁

両刃包丁は、左右両方に刃がついたV字型の断面構造を持っています。
片刃に比べると切れ味はややマイルドですが、利き手を選ばず使え、野菜をまっすぐ押し切る・刻むといった家庭料理では非常に扱いやすい構造をとっていると言えます。
先にも述べたように、現代ではステンレス製の両刃タイプ菜切り包丁が量販店や通販で主流になっており、洋包丁に近い感覚で使える点が特徴です。

【タイプ別】砥石を使った菜切り包丁の正しい研ぎ方(角度・手順)
それでは、砥石を使った菜切り包丁の正しい研ぎ方について片刃、両刃構造タイプそれぞれで解説していきましょう。
この違いを理解しないまま自己流で研いでしまうと、切れ味が落ちるだけでなく、刃先を痛めたり、研ぎ減りを早めてしまう原因にもなりますのでしっかり把握しておきましょう。
砥石を使った片刃タイプ菜切り包丁の研ぎ方
片刃包丁は、表側(右利き用の場合は右面)に大きな斜面(切刃)があり、裏側は平面+裏スキという非対称構造。そのため、表と裏で研ぎ方が全く異なります。
研ぎ方の流れ、手順は以下の通り。
- 砥石に対して刃を寝かせ気味(角度目安:約15°)で、表面の切刃全体を砥石に密着させる
- 刃元から刃先にかけて、押し引きで均等に研ぐ(力は押すときだけ)
- 研ぎでバリ(返り)が出てくるので裏面をほぼ水平に当てて裏押しをし、バリを丁寧に取り除く
- 必要に応じて仕上げ砥石で最終研ぎを行う
片刃タイプの菜切り包丁を研ぐときは、まず表の切刃全体を砥石にしっかり密着させ、角度を固定して研ぐことが重要。力を入れすぎず、砥石の表面を滑らせるように均等な圧力で研ぎ進めます。
ある程度研ぐと、裏側に薄い金属の返り(バリ)が出てくるので、包丁を裏返して裏面を砥石に水平に当て、バリを丁寧に取り除きます。これを怠ると刃先が鈍くなり、切れ味が安定しません。最後に仕上げ砥石で軽く整えることで、より鋭く滑らかな刃に仕上がりますよ。
【必要か】仕上げ砥石はむしろ切れなくなる?いらない場合と必要な場合を見極めよう

砥石を使った両刃タイプ菜切り包丁の研ぎ方
左右対称のV字型の断面構造を持った両刃タイプ菜切り包丁を砥石で研ぐ場合の手順は以下の通りです。
- 左右それぞれ15〜20°の角度を保ち、片面ずつ研ぐ
- 片面を5〜10回研いだら、反対側も同じ回数を研ぐ
- 左右交互に研いで刃先の中心を整える
- 最後に軽く仕上げ研ぎをしてバリを除去する
このように片刃と違って裏押しの工程は必要ありませんが、左右を均等に研ぐことが最大のポイントになります。
角度は片側15〜20°を目安にし、砥石に対して均一に当てて研ぎます。片面を数回研いだら、反対面も同じ回数・同じ角度で研ぐことで、刃先が中央に維持され、安定したV字に仕上がります。
そして研ぎ終わりに両面から軽く仕上げ研ぎを行い、細かいバリを落として完了となります。両刃は片刃に比べて構造的に扱いやすく、初心者でも研ぎやすいのが特徴です。
【実用比較】菜切り包丁にシャープナーは有効?砥石との使い分け方
菜切り包丁も、シャープナーで手軽に研げるのかについては初心者が抱く典型的な疑問です。
結論からいえば、両刃タイプの菜切り包丁であればシャープナーは日常的なメンテナンス手段として有効ですが、一方で、片刃タイプの場合は構造上の理由から基本的におすすめできません。
包丁のタイプによって仕上がりや刃先の状態が大きく変わるため、それぞれの特徴と限界を理解したうえで、シャープナーと砥石を使い分けることが重要です。以下にて詳しく見ていきましょう。
片刃タイプとシャープナーの相性は基本的に悪い
片刃の菜切り包丁は、片側のみに大きな斜面(切刃)があり、裏面はほぼ平面で中央に裏スキと呼ばれる浅い凹みがある独特の構造を持ちます。
一方、一般的な家庭用シャープナーは、両刃包丁を前提に左右対称のV字型の溝で刃を挟み込み、一定の角度で研ぐ仕組み。つまり、構造そのものが片刃用に作られていないため、正しく研ぐことができません。
特に問題になるのは、シャープナーでは裏面の処理(裏押し)が全くできない点。片刃包丁の切れ味は、この裏押しによってバリを取り、刃先をまっすぐ整える工程に大きく依存しています。シャープナーで無理に片刃包丁を引くと、裏スキが削れて本来の性能が損なわれたり、刃先が丸くなって切れ味がかえって落ちてしまうことも。
また、シャープナーは角度が固定されているため、片刃包丁が持つ独特の片側15°前後の角度を再現することも不可能です。そのため、切れ味を正しく戻すどころか、刃の形状を崩してしまう危険性があります。
応急処置的に軽く引く程度であれば一時的に切れ味が改善する場合もありますが、根本的な研ぎ直しにはなりません。片刃タイプの菜切り包丁をきちんと研ぐには、砥石を使って正しい角度と裏押しを行う方法が基本になります。
両刃タイプはシャープナーと好相性。砥石との併用が理想
両刃タイプの菜切り包丁は、左右対称のV字構造を持つため、シャープナーと非常に相性が良いのが特徴。
刃を差し込んで一定方向に引くだけで、シャープナーの固定角度に沿って刃先が整えられるため、初心者でも簡単に軽い研ぎ直しや切れ味の維持が可能です。特別な技術や角度調整の知識がいらないので、日常的なメンテナンスには非常に便利な方法といえます。
ただし、シャープナーには限界も。大きな刃こぼれや丸刃の修復には対応できず、シャープナーを繰り返し使用することで刃先の角度が次第に鈍角になっていく傾向があります。これは、シャープナーの溝の角度が固定されているため、微妙な角度調整ができないため。そのため、長期的に見れば切れ味が次第に落ち、刃先が厚ぼったくなってしまう場合があります。
総括して両刃タイプの菜切り包丁では、シャープナーを日常的な簡易メンテナンスとして活用しつつ、定期的に砥石で刃先を正確に整える併用スタイルが理想的です。
【危険?】包丁にシャープナーはダメ?メリット・デメリットを徹底解説

砥石の仕上がりとシャープナーの手軽さを両立するEDGBLACK
菜切り包丁を正しく研ぐためには、片刃と両刃で異なる角度を維持し、刃の状態に合わせた丁寧な作業が欠かせません。従来の砥石を使った研ぎは、切れ味や仕上がりの面で優れていますが、安定した角度を保つのが難しく、初心者にとってはハードルが高いものでした。
一方で、シャープナーは扱いやすく短時間で切れ味を戻せるものの、角度調整ができず、刃の状態によっては十分な効果を発揮できないという制限がありました。
我々のEDGBLACKは、こうした従来の二択にとらわれない、新しい研ぎスタイルを提案しています。
EDGBLACKの研ぎツールは、0〜50°の角度調整機構を備えることで、包丁の種類や状態に合わせた最適な研ぎを可能にします。 片刃・両刃を問わず、菜切り包丁の特性に応じた角度を正確に再現できるため、従来のシャープナーでは難しかった精密な仕上がりを実現できます。
特に片刃包丁は寝かせ気味の角度で切刃を正確に研ぐ必要がありますが、この調整機構があれば、初心者でも迷わず最適な角度を設定することができます。
さらにEDGBLACKは、砥石ローラーや高品質砥石を活用することで、砥石研ぎに匹敵する鋭い仕上がりと、シャープナーのような手軽さを両立。包丁を固定してローラーを転がすだけで均一な研ぎが可能なため、従来の砥石研ぎのように熟練した手の動きや複雑な角度の維持は必要ありません。
それでいて砥石の粒度を活かした本格的な仕上げができるため、片刃の菜切り包丁の繊細な刃付けにも対応し、両刃包丁ではシャープナー以上に安定した切れ味の復活が期待できます。
従来の砥石かシャープナーかという二者択一では満足できなかったユーザーにとって、EDGBLACKの研ぎツールはまさに第三の選択肢といえる存在。砥石の精密さ、シャープナーの扱いやすさ、そして自由な角度調整という要素を兼ね備えたいいとこづくめの製品ですよ。
【注意】菜切り包丁の研ぎ方は間違えやすい?:まとめ
一見シンプルに見える菜切り包丁ですが、片刃・両刃の構造や歴史的背景をたどると、その扱いには一定の知識と工夫が必要です。
片刃包丁は裏スキを活かした鋭い切れ味と直進性が魅力ですが、研ぎには正確な角度維持と裏押しが欠かせません。両刃包丁は扱いやすく万能性が高い一方で、左右のバランスを意識した研ぎが求められます。いずれも構造を理解したうえで、適切な角度と手順で研ぐことが、切れ味を維持する秘訣です。
また、シャープナーと砥石はそれぞれに得意分野が異なります。片刃の菜切り包丁では砥石による正確な研ぎが基本となり、両刃タイプではシャープナーを活用した日常的なメンテナンスと砥石研ぎの併用が最も現実的な選択。
菜切り包丁のタイプと目的に合わせて、道具を上手に使い分けることが、研ぎを無理なく続けるコツといえるでしょう。
さらに近年では、我々のEDGBLACKのように角度調整機能や砥石ローラーを組み合わせ、砥石の精度とシャープナーの手軽さを両立させた革新的な研ぎツールも登場しています。砥石かシャープナーどちらか一方に頼るスタイルから一歩進んで、自分の包丁と使い方に合った最新機器を取り入れてみてはいかがでしょうか?
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /








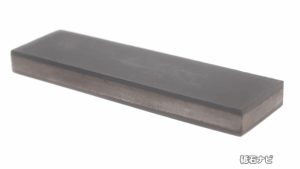

コメント