【10選】天然砥石の種類まとめ!最高級品から産地ごとの特徴まで徹底解説

「天然砥石って種類が多すぎて、どれを選べばいいのか分からない…」
「包丁や鉋に合った砥石を選びたいけど、産地ごとの特徴が難しそう…」
そう悩む方は多いでしょう。
天然砥石は、仕上がりの美しさや刃の切れ味を格段に高めてくれる一方で、産地・層・粒度によって性質が大きく異なるため、初心者にとっては選び方が難しい道具です。
そこで今回は「天然砥石の種類10選と、産地ごとの特徴」を徹底解説します。
本記事では、プロが愛用する最高級砥石から、家庭用でも扱いやすい定番モデルまでを網羅的に紹介し、失敗しない選び方のポイントを詳しく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
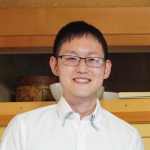
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

天然砥石の種類
まずは天然砥石の種類をまとめていきます。特に有名な砥石10個に絞って解説していきますね。
- 中山(なかやま)〔仕上げ〕
- 奥殿(おくど/おづく)〔仕上げ〕
- 菖蒲谷(しょうぶだに)〔仕上げ/巣板など〕
- 大平山(おおひら)〔内曇・巣板/仕上げ〕
- 鳴滝(なるたき)〔仕上げ/コッパ含む〕
- 丹波青砥(たんばあおと)〔中砥〕
- 天草砥(あまくさ)〔荒砥〜中砥〕
- 伊予砥(いよと/伊予銘砥)〔荒砥〜中砥〕
- 会津砥(あいづと)〔中〜仕上げ
- 対馬砥(つしま)〔黒名倉・仕上げ〕
順番に見ていきましょう。
種類①:中山(なかやま)
京都・梅ヶ畑地区で採掘される中山砥石は、世界的にも評価される最高級の天然仕上げ砥石です。
粒子が極めて細かく均一なため、包丁や鉋、鑿などの刃先を鏡面のように磨き上げることができ、切れ味と耐久性を両立させることができます。
中山の砥石は「赤ピン」や「戸前」などの層名によって性質が異なり、硬口から中硬口まで幅広い研ぎ感が存在します。滑らかで金属に優しい研ぎ味は、プロの研師が最終工程で最も信頼する理由の一つです。
また、金属表面の微細な凹凸を整えることで刃先の鋭さが長持ちし、日常の包丁研ぎにも応用可能。価格は数万円から数十万円に及ぶこともあり、希少な大判サイズは70万円を超える場合もあります。
種類②:奥殿(おくどの)
奥殿砥石は、中山と並び称される京都本山系の高級仕上げ砥で、刃物の最終工程に最適な天然砥石です。
粒度が非常に細かく、金属表面を微細に削ることで刃先の鋭さと美しさを最大限に引き出します。特に「白巣板」「羽二重」などの層名を持つ個体は人気が高く、適度な硬度と研磨力のバランスが絶妙です。
金属との摩擦が少なく、均一な研ぎ面を作りやすいため、初心者から上級者まで幅広く扱えます。研ぎ跡が極めて美しいのも特徴で、包丁だけでなく日本刀や和鋏など繊細な刃物の仕上げにも適しています。
価格は1万円台の入門品から50万円を超える特級品まで幅広く、中山よりもやや軽い研ぎ心地が特徴で、滑らかさと仕上がりの美しさを重視する研師に好まれています。
種類③:菖蒲谷(しょうぶだに)
菖蒲谷砥石は、京都本山系の中でもやや柔らかめの仕上げ砥として知られ、繊細な仕上がりを求める職人に人気があります。
研磨力が高すぎず、金属を優しく削るため、刃先を傷つける心配がほとんどありません。巣板や浅黄といった層によって性質が異なり、用途や研ぎ味に応じて選び分けられる点も特徴です。
特に「巣板系」は仕上がりの光沢が優れており、刀剣研磨にも使われます。中山や奥殿よりも価格が比較的抑えられているため、プロだけでなく中級者にも人気が高いです。
研ぎ面が均一に整いやすく、刃先のエッジも綺麗に仕上がるため、切れ味の再現性が非常に高いのが魅力です。柔らかい研ぎ感は扱いやすく、研ぎの微調整や最終段階の艶出しなど、細やかな仕上げを必要とする作業にも最適です。
繊細さと扱いやすさを両立したバランスの良い砥石といえるでしょう。
種類④:大平(おおひら)
大平山砥石は、京都の「内曇(うちぐもり)」や「巣板」などの層が採れる砥石で、主に高精度な仕上げ作業に用いられます。
粒子が非常に細かく、刃先を滑らかに整えることができるため、仕上がりは鏡面に近い状態になります。硬口の個体が多く、金属としっかり噛み合う感覚があるため、精密な角度調整や切れ味の微調整が可能です。
特に鉋や鑿など、精密さを要求される工具の最終研ぎで力を発揮します。摩耗しにくく、長寿命である点も評価が高く、長く使える一生ものの砥石として購入されることが多いです。
中山系の中でも流通量がやや少ないため希少価値が高く、価格も高めですが、その分性能は安定しており、信頼性の高い砥石として多くの職人から選ばれています。
種類⑤:鳴滝(なるたき)
鳴滝砥石は、京都の伝統的な砥石産地で採掘される仕上げ砥のひとつで、柔らかい研ぎ心地と扱いやすさが特徴です。
金属への当たりが軽く、刃先に負担をかけずに仕上げることができるため、細かい刃先の調整や艶出しに向いています。サイズの小さい「コッパ」としても流通しており、携帯用や補助研ぎ用としても使いやすいのがメリットです。
包丁・鑿・鉋といった日常的な刃物はもちろん、日本刀や伝統工芸の仕上げにも使われるほどの品質を持っています。中山や奥殿に比べると入手しやすく価格も控えめで、コストパフォーマンスに優れた仕上げ砥として評価されています。
刃物の表面を均一に整える力が強く、切れ味だけでなく見た目の美しさにもこだわりたい人にとって理想的な砥石といえるでしょう。
種類⑥:丹波青砥(たんばあおと)
丹波青砥は、兵庫県丹波地域で採掘される日本を代表する天然中砥石です。
粒度はおよそ#800〜#1500とされ、荒研ぎの後、仕上げ砥石に進む前の「中間工程」に最適な砥石です。人工中砥と比較すると削れ方が柔らかく、刃先へのダメージが少ないのが特徴です。
特に料理包丁や鉋、鑿など日常的な刃物との相性が良く、刃持ちを向上させる効果も期待できます。中砥石は研ぎの全工程の中で最も使用頻度が高いため、丹波青砥のような天然中砥を使用することで、研ぎ上がりの精度や刃の寿命が大きく変わってきます。
現在も比較的入手しやすく、価格帯も幅広いため、天然砥石の入門として選ばれることが多いのも特徴です。プロ職人から一般家庭まで幅広く愛用されており、日本の研ぎ文化を支える砥石といえるでしょう。
種類⑦:天草砥(あまくさ)
天草砥は熊本県で採掘される天然砥石で、主に荒研ぎから中研ぎの工程で使用されます。
粒度は#200〜#800程度とやや粗めで、刃こぼれの修正や刃の角度調整、形状の整形といった初期作業に向いています。天然砥石らしい「削れる感覚」が強く、短時間で効率よく金属を削ることができるため、欠けた刃の再生や新品刃物の成形にも最適です。
また、サイズが大きく入手しやすいため、家庭用から業務用まで幅広く活用されています。天草砥の大きな特徴は、金属を削る力が強いにもかかわらず、刃先への負担が比較的少ない点です。これにより、荒研ぎ段階でも刃の損傷を最小限に抑えることができます。
価格も手ごろなため、荒研ぎ用として一本持っておくと大変便利です。
種類⑧:伊予砥(いよと)
伊予砥は愛媛県で産出される天然荒砥石で、古くから日本国内で広く利用されています。
粒度は#300〜#800程度と粗めで、主に刃先の形状修正や欠けの修復、荒削りといった初期段階の作業に使用されます。研磨力が非常に高く、大量の金属を短時間で削ることができるため、効率性に優れた砥石といえます。
柔らかめの石質は刃への当たりが優しく、刃先を痛めにくいのも魅力です。包丁や鉋、鑿だけでなく、園芸用の刃物や農具の研ぎなどにも広く使われており、実用性の高さが特徴です。
サイズが大きく安定性が高いため、長時間の研ぎ作業にも適しています。価格も比較的手ごろで、天然砥石を初めて購入する人にも人気があります。
種類⑨:会津砥(あいづと)
会津砥は福島県会津地方で採掘される天然砥石で、中砥から仕上げの中間領域まで幅広く使用できる万能型砥石です。
粒度は#1000〜#3000とされ、刃先を滑らかに整えながら切れ味と耐久性を高めることが可能。研ぎ味は非常に柔らかく、初心者でも扱いやすいのが特徴です。
研磨面が均一に仕上がるため、仕上げ砥石へ移行する前段階として理想的な下地が作れます。会津砥は、かつて日本刀研磨にも使用されてきた歴史を持ち、今でも刀匠や職人に愛用されています。
人工中砥に比べると研ぎ時間はやや長くなりますが、その分、仕上がりの美しさと刃の持ちが格段に向上します。入手も比較的容易で、価格も天然砥石としては手ごろなため、プロからアマチュアまで幅広く使用されています。
種類⑩:対馬砥(つしま)
対馬砥は長崎県・対馬で採掘される天然砥石で、「黒名倉」と呼ばれる補助砥として特に有名です。
粒度は非常に細かく、仕上げ工程や仕上げ前の調整、あるいは他の砥石の泥出し用として使われます。対馬砥の研磨力は控えめながらも非常に繊細で、刃先の微細な凹凸を整え、仕上げ砥の効果を最大限に引き出す役割を持ちます。
また、摩耗しにくく耐久性が高いため、長期間使用しても性能がほとんど落ちません。単体での使用だけでなく、仕上げ砥と組み合わせて刃先の精度を高める「サポート砥石」としての役割も重要です。
刀剣研磨や高級包丁の仕上げなど、精度が要求される作業で特に力を発揮します。天然砥石の工程をより高精度に仕上げたい場合、対馬砥は極めて有効な砥石となります。
>>【比較】砥石とシャープナーの違いは?7項目からどっちがいいのかを徹底比較

天然砥石と人工砥石の違いは?
次に、天然砥石と人工砥石の違いをまとめていきますね
- 天然砥石は地層から採掘された自然の石で、人工砥石は工業的に製造された砥材で作られる。
- 天然砥石は粒子の大きさや硬さに個体差があり、人工砥石は粒度が均一で仕上がりが安定している。
- 天然砥石は研ぎ味が滑らかで刃物の切れ味が長持ちしやすく、人工砥石は研磨力が強く短時間で削れる。
- 天然砥石は希少性が高く高価になりやすく、人工砥石は量産可能で価格が比較的安い。
- 天然砥石は熟練者向けで扱いに技術が必要、人工砥石は初心者でも扱いやすい。
順番に見ていきましょう。
違い①:素材と製法
天然砥石は地層から切り出された岩石を整形したもので、自然由来の鉱物が複雑に混在しています。人工砥石は酸化アルミニウムや炭化ケイ素、ダイヤモンド砥粒などを結合材で固め、狙った特性を設計的に与えた工業製品です。
前者は層や鉱脈の違いが研ぎ味に現れ、同じ産地でも個体差が出ます。後者は配合や焼結条件を管理するため、狙い通りの硬さや切削性を再現しやすい構造です。
そのため、天然は唯一無二の研ぎ心地と表情、人工は仕様に応じた性能の作り分けが可能という位置づけになりますね。
違い②:粒度の均一性と再現性
天然砥石は自然の堆積・変成によってできるため、砥粒の大きさや分布が石ごとに異なります。粒度表記がないことも多く、同名でも硬口・軟口の幅があり、再購入時に同じ感覚を得られない場合もあります。
人工砥石は番手で粒度を管理しやすく、同じ型番なら研ぎ上がりの再現性が高い点が強みです。複数人や複数拠点で同一品質を求める現場では、人工の均一性が効いてきます。
一方で、天然は粒度のムラが適度な当たりの柔らかさにつながり、金属表面の微細な整え方に独特の味わいをもたらすことがあります。
違い③:研ぎ味や仕上がり
天然砥石は当たりが滑らかで、金属を「削る」というより「撫でて整える」感覚に近い研ぎ味が得られます。細かな傷が伸びやすく、艶の出方やエッジの立ち上がりが自然で、切り込みの軽さや刃持ちの良さにつながりやすい傾向です。
人工砥石は砥粒が均質に働くため、除去量が読みやすく、短時間で狙いの面精度に近づけます。荒・中・仕上げの各工程を段階的に揃える運用に向く構成です。
なので、スピードや段取り重視なら人工、仕上がりの質感や微妙な刃先表現を求めるなら天然が良いでしょう。ただ、個体差や番手設計で逆転する場面もあります。
違い④:価格やメンテナンス性
天然砥石は採掘量や品質のばらつきから希少性が価格に反映されやすく、産地や層、サイズによって相場が大きく動きます。評価の定まった個体は高値で推移しがちで、同規格を複数枚そろえるのは難題になりやすい現実です。
人工砥石は量産によって入手性が安定し、同型番を必要数そろえやすく、交換・補充の計画も立てやすい構造です。
面直しやメンテナンスでは、人工はダイヤモンド砥石や修正砥との相性が読みやすく、天然は石質に合わせた当て方や泥の使い方が問われますね。
違い⑤:使いやすさ
天然砥石は石ごとの個性を読み取り、当たり圧や角度、泥の出し方を調整する力が仕上がりを左右します。習熟が必要ですが、フィットした個体に出会えれば替え難い成果を得やすいです。
人工砥石は番手体系に沿って工程設計しやすく、初心者でも再現可能なルーティンを組み立てやすいメリットがあります。工房や厨房の標準化、複数人での共有運用、短時間での結果重視には人工が噛み合うでしょう。
なので、作業スピード・再現性・質感のどこを重視するかで配分を決める発想が実務的です。現場では人工で土台を作り、天然で質感を整える併用設計も有効でしょう。
>>【比較】100均のおすすめ包丁研ぎ3社!セリア・ダイソー・キャンドゥの砥石を徹底比較

料理人でなければ、人工砥石の方が安く使いやすい
包丁を研ぐと聞くと「難しそう」「プロ向け」と感じる人が多いかもしれませんが、家庭料理レベルなら天然砥石にこだわる必要はありません。
天然砥石は一つひとつ性質が異なり、研ぎ方も個体差に合わせる必要があるため、料理人のように使いこなすには経験と技術が必要です。
その一方で、人工砥石は粒度が均一で扱いやすく、再現性が高いため、誰が使っても安定した切れ味を再現できるのが大きなメリット。コストも天然より圧倒的に抑えられ、家庭用としては実用性が高いと言えるでしょう。
人工砥石ならEDGBLACKがおすすめ
中でも、「EDGBLACK」は、人工砥石の中でも家庭向けに特化した構造で、“砥石なのにシャープナーのように使える”という点が大きな魅力です。
#360(荒研ぎ)、#600(中研ぎ)のダイヤモンド砥石と、#1000(仕上げ)のセラミック砥石がセットになっており、刃こぼれの修正から日常の仕上げまで一台で完結します。
刃は磁力で固定され、角度も0〜50°まで自在に調整できるため、初心者でも正しい角度で安定した研ぎが可能です。
天然砥石の種類まとめ:まとめ
天然砥石は、日本刀の研ぎから料理包丁の仕上げまで幅広く使われてきた伝統的な道具であり、中山や奥殿、菖蒲谷といった仕上げ砥から、丹波青砥や天草砥などの中砥・荒砥まで、種類ごとに役割と特性が異なります。
それぞれに個性があり、研ぎ味や仕上がりにこだわる職人にとっては欠かせない存在です。しかし、粒度や性質に個体差があるため、初心者には扱いが難しいのも事実です。
もし家庭で手軽に切れ味を整えたいなら、粒度が均一で再現性が高く、誰でも安定した研ぎができる人工砥石を選ぶのが現実的でしょう。
中でも「EDGBLACK」は、砥石本来の性能とシャープナーの手軽さを兼ね備えたモデルとして人気が高く、初心者から上級者まで幅広い層に支持されています。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /










コメント