【最高級】天然砥石のおすすめ10選!産地や種類、特徴や見分け方まで徹底解説!

包丁やナイフの切れ味を最大限に引き出すなら、人工砥石では味わえない天然砥石の存在は欠かせません。天然砥石は、地層ごとに異なる粒度や研ぎ感を持ち、同じ種類でも一つとして同じ石がないのが最大の特徴。その奥深い魅力から、昔から料理人や職人たちに愛用されてきました。
しかし「種類が多くて違いが分からない…」「本当に良い砥石はどれなのか」と迷う方も多いはず。今回は、天然砥石のおすすめ10選を厳選し、産地や種類ごとの特徴、さらに見分け方のポイントまで徹底解説します。
初心者でも扱いやすい中砥から、プロが手にする最高級仕上げ砥まで網羅的に紹介しますので、あなたの包丁ライフに最適な一本がきっと見つかるでしょう。
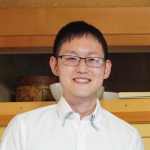
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

天然砥石の基礎知識
まずは、そもそも天然砥石に関しての基礎知識についてこちらで確認しておきましょう。
人工砥石の違いや粒度による役割、産地ごとの特色をそれぞれ説明していきます。
天然砥石と人工砥石の違い
天然砥石は自然の地層から切り出され、一本ごとに個性を持ちます。粒子の形や硬さが均一ではないため、研ぎ味は繊細で、刃物に独特の粘りや冴えを与えられるのが魅力です。料理人や職人に長年愛されてきた理由もここにあると言えます。
一方で人工砥石は砥粒を人為的に焼き固めたもので、粒度や硬さが均一。扱いやすく価格も安定しているため、初心者にも手が出しやすい存在です。
要するに、どちらが適しているかは用途や目的次第と言うことです。
粒度の役割
砥石はその粒度によって大きく以下の3つに分けられます。
- 荒砥
- 中砥
- 仕上げ砥
荒砥は研削力が強く、刃欠けの修正や刃形の整えに用いられるのに対して、中砥は日常的な研ぎ直しに最も適しており、切れ味を安定させる役割を担います。
そして仕上げ砥は最終段階で使い、刃先を鋭く、場合によっては鏡面のように仕上げることができます。
天然砥石の場合は人工砥石ほど粒度が明確ではないものの、その曖昧さがかえって自然な研ぎ上がりや持続性に繋がるとされます。
産地ごとの特色
天然砥石は産地によって大きくその特徴が異なります。
- 京都(山城地域)
- 丹波青砥(京都・亀岡)
- 伊予砥(愛媛・砥部)
- 会津砥(福島)
- 大村砥(和歌山〈旧来は長崎〉)
京都の山城地域は世界的に名高い仕上げ砥の産地で、中でも正本山合砥は職人から高い評価を受けています。
丹波青砥はなめらかな研ぎ感を持つ中砥として知られ、伊予砥はやや柔らかく扱いやすいため家庭用に人気があります。会津砥は中砥から仕上げ域まで幅広く対応でき、特に和包丁との相性が良いとされます。
大村砥は代表的な荒砥で、刃欠け修正や形直しに力を発揮します。
要するに各産地で荒砥、中砥、仕上げ砥どれかの領域に特化した歴史的名ブランドを抱えているイメージ。次項ではそれぞれ網羅的に紹介していきます。
【14選】ホームセンターのおすすめ砥石!コーナンやニトリ、ドンキホーテでも買える?

【荒砥(荒研ぎ用)編】おすすめの天然砥石
それでは、各粒度に応じた伝統的に名を残す代表的な砥石を厳選し、それぞれの特徴を解説していきましょう。
まずは荒砥(荒研ぎ用)から。
- 大村砥(和歌山〈旧来は長崎〉)
- 平島砥(長崎)
それぞれ順番に見ていきましょう。
【荒砥(荒研ぎ用)】おすすめの天然砥石①:大村砥(和歌山〈旧来は長崎〉)
大村砥は、かつて長崎県大村市周辺で産出された歴史を持ち、現在は和歌山県白浜町が主な産地として知られる代表的な天然荒砥。粒度が粗く硬度も高いため、刃欠けした包丁や大きく丸まった刃の形を短時間で修正するのに適しています。
研削力が強い一方で、刃に無駄な傷を残しにくい点も評価されており、日本刀の研磨工程や伝統工芸の現場でも重宝されてきました。一般家庭で常用する砥石というよりは、プロや研ぎに慣れた人が荒研ぎ専用として使うのにふさわしい砥石。天然荒砥の中でも実用性が高く、天然砥石の導入としても選ばれる存在です。
【荒砥(荒研ぎ用)】おすすめの天然砥石②:平島砥(長崎)
平島砥は長崎県西彼杵郡の平島で採掘されてきた天然超荒砥。粒子が非常に粗いため、刃の欠けや大きな刃こぼれを効率的に整えることができます。特徴は研削力の強さにあり、数回の研ぎで大きな欠損を修復できるほどの力を持ちます。
そのため、日本刀の研磨や包丁の刃の再生工程など、通常の荒砥では力不足になる場面で力を発揮。ただし硬度は比較的柔らかめで減りが早いため、日常的な使用よりも修正専用として活用するのが適切です。
天然砥石ならではの研ぎ感を持ちながら、荒研ぎ領域に特化した希少な砥石として広く知られています。
【中砥(日常研ぎ用)編】おすすめの天然砥石
続いては、中砥(日常研ぎ用)でのおすすめ天然砥石について。
- 丹波青砥(京都・亀岡)
- 伊予砥(愛媛・砥部)
- 会津砥(福島)
こちらも順番に見ていきましょう。
【中砥(日常研ぎ用)編】おすすめの天然砥石①:丹波青砥(京都・亀岡)
丹波青砥は、京都府亀岡市周辺で産出される天然中砥で、天然砥石の中でも特に名高い存在です。その名の通り青みがかった石肌を持ち、粒子が細かく均一で、なめらかな研ぎ味を生み出します。
日常的な研ぎ直しに最も適しており、切れ味を安定させながらも、仕上げ砥に移行するための下地づくりにも活躍。家庭用包丁から和食料理人が使う出刃・柳刃などの和包丁まで幅広く対応可能で、天然砥石を初めて使う人にも扱いやすいのが特徴です。
天然中砥の代名詞といえる存在で、安定した品質と研ぎ感から、今も多くの刃物職人や愛好家に選ばれています。
【中砥(日常研ぎ用)編】おすすめの天然砥石②:伊予砥(愛媛・砥部)
伊予砥は愛媛県伊予郡砥部町で産出される天然中砥で、その歴史は古く、日本最古の砥石ともいわれるほど長い伝統を持ちます。やや柔らかめの性質を持つため、研ぎ味が優しく、初心者でも角度を安定させやすいのが特徴。
包丁の切れ味を日常的に回復させたいときに適しており、鋭さを求めるよりも扱いやすさと安定性に優れた砥石といえます。また、伊予砥は日本国内だけでなく海外にも知られており、そのコストパフォーマンスの良さから愛好家も数多く存在。
天然中砥の中でも入手しやすく、家庭からプロまで幅広い層に支持される砥石ですよ。
【中砥(日常研ぎ用)編】おすすめの天然砥石③:会津砥(福島)
会津砥は福島県会津地方で産出される天然砥石で、中砥から中仕上げ域にかけて活用できるのが大きな特徴です。粒子が細かく、適度な硬さを持つため、研ぎ味は心地よく、刃物の表面を滑らかに整えながら鋭さを引き出します。
特に和包丁との相性が良いとされ、出刃包丁や刺身包丁を日常的に研ぐ際に用いられています。会津砥は研削力と仕上げ力のバランスに優れており、一本持っておけば幅広い用途に対応できる万能砥石です。
料理人だけでなく趣味で包丁研ぎを楽しむ人にも人気が高く、こちらも天然中砥の中でも実用性の高さで評価される存在です。
【仕上げ砥(最終仕上げ用)編】おすすめの天然砥石
最終仕上げに用いられる仕上げ砥についてのおすすめ天然砥石は以下の4つ。
- 京都・山城合砥(本山系)
- 正本山合砥(京都)
- 鳴滝砥(京都・右京区)
- 戸前(京都・層名)
【仕上げ砥(最終仕上げ用)編】おすすめの天然砥石①:京都・山城合砥(本山系)
京都・梅ヶ畑を中心とした山城地域は、世界的に名高い天然仕上げ砥の一大産地。その中でも山城合砥は、粒度が極めて細かく、刃先を鏡面のように仕上げられる点で高く評価されています。
鋼材を選ばず、包丁から鉋や鑿といった大工道具まで幅広く対応できる汎用性の高さも特徴。研ぎ上がりの切れ味は鋭く、刃持ちが長続きすることから、寿司職人や和食料理人をはじめ、多くのプロが愛用しています。
日本の伝統工芸を支えてきた最高級仕上げ砥の代表格であり、天然砥石の魅力を体感するなら欠かせない存在です。
【仕上げ砥(最終仕上げ用)編】おすすめの天然砥石②:正本山合砥(京都)
「正本山」とは、京都本山系で産出される天然砥石の中でも、特に品質が安定したものを指す伝統的な呼称です。産地や銘柄というよりは品質保証の印に近く、江戸時代から最高級仕上げ砥の代名詞とされてきました。正本山合砥は粒子が非常に均一で、研ぎ感が滑らかであるため、刃先を均質に仕上げられるのが特徴です。
そのため、寿司職人や和食料理人の間で圧倒的な信頼を得ており、プロの現場ではまさに憧れの存在。価格は高価ですが、それに見合うだけの切れ味と仕上がりを提供してくれる砥石ですよ。
【仕上げ砥(最終仕上げ用)編】おすすめの天然砥石③:鳴滝砥(京都・右京区)
鳴滝砥は京都市右京区鳴滝地域で産出された天然仕上げ砥で、古くから名砥として知られています。やや硬めの性質を持ち、鋭く冴えた切れ味に仕上がるのが特徴です。特に和包丁や日本刀の最終仕上げに使われることが多く、その切れ味の冴えはプロの料理人や刀剣研師からも高く評価。
産出量は限られており、現在市場に出回る数は少ないため希少性がかなり高いですが、その分手に入れる価値のある砥石として愛好家から支持されています。天然仕上げ砥の奥深さを象徴する存在と言えるでしょう。
【仕上げ砥(最終仕上げ用)編】おすすめの天然砥石④:戸前(京都・層名)
戸前とは、京都本山系で採れる天然仕上げ砥の地層名を指します。この戸前層から産出される砥石は「戸前砥」と呼ばれることもありますが、正確には銘柄というより地質層の名称に由来。戸前層の砥石は硬口で粒子が引き締まっており、鋭く冴えた切れ味を出しやすいのが大きな特徴です。
とりわけ硬質な鋼材を用いた和包丁や大工道具の最終仕上げに適しており、職人たちから高く評価されています。層ごとの個性を理解することで、京都天然仕上げ砥の奥深さをより深く味わうことができるでしょう。
【番外編】おすすめの天然砥石-阿波(徳島)
ここまで紹介した砥石は、現在も一定の流通がある代表的な産地ですが、歴史の中には今ではほとんど姿を消した砥石も存在します。
その一つが徳島県で採掘されていたとされる阿波砥。日本各地で育まれた砥石文化の歴史や多様性を語る上では欠かせません。阿波砥は、かつて地域の刃物職人や日用品の研ぎに用いられていたと伝わりますが、現在では市場に出回ることはほとんどなく、史料や記録に名を残す程度。
阿波砥が今は採れない理由
阿波砥が現在ほとんど流通していないのには、いくつかの背景があります。
まず、採掘量そのものが限られていたため、時代とともに鉱脈が枯渇し、継続的な採掘が難しくなったと考えられます。さらに、昭和以降は人工砥石の登場によって安価で均質な製品が広く普及し、天然砥石の需要が大きく減少しました。採掘現場の人員確保や採算性の問題もあり、徳島における砥石産業は自然と衰退していったのです。
このような歴史的背景から、阿波砥は現代では使うための砥石ではなく、かつて日本各地に砥石文化が根付いていたことを示す歴史的遺産として語られる存在となっています。
天然砥石の選び方・注意点
天然砥石は一本ごとに個性があり、価格も大きく異なるため、初めて購入する方にとっては選び方が難しいものです。
最後に、購入前に押さえておきたい重要なポイントを整理しました。それは以下の4つ。
- 価格帯
- サイズ
- 包丁との相性
- メンテナンス性
天然砥石は数千円から数十万円まで幅広い価格帯で流通。特に仕上げ砥は希少性が高く、高額になりやすい点を理解しておく必要があります。サイズも重要で、小さい砥石は取り回しやすいものの安定性に欠けるため、刃渡りの長い包丁を使う場合は大きめの砥石を選んだ方が安心です。
また、包丁との相性も軽視できません。特に和包丁や高級鋼材の刃物は天然砥石の研ぎ味を活かしやすい一方で、ステンレス製の量産包丁であれば人工砥石でも十分なケースも。加えて、天然砥石は個体差が大きいため、使ううちに表面が凹んだり傾いたりすることもあります。そのため、平面を維持するための面直しなど定期的なメンテナンスが必須となります。
天然砥石を選ぶ際は、こうした条件を照らし合わせながら、自分の包丁や使用スタイルに合った一つを見極めることが大切です。
【切れ味最強】恐ろしく切れる包丁!切れ味ランキングTop.7を紹介します

天然砥石が難しいと感じる方へ:EDGBLACKという選択肢
天然砥石は確かに魅力的ですが、実際に使ってみると「角度を安定させられない」「粒度の違いを理解するのが難しい」と悩む方も少なくありません。さらに、価格が高額になりやすく、手入れに手間がかかる点も初心者にとっては大きなハードル。
そこで注目したいのが、砥石の本格的な研ぎ味とシャープナーの手軽さを兼ね備えた EDGBLACK Knife Sharpener です。15度・18度・20度・22度という4種類の角度に対応し、家庭用包丁からアウトドアナイフまで幅広い刃物を正確に研ぐことができます。
さらに、#360・#600のダイヤモンド砥石と#1000のセラミック砥石を搭載しており、荒研ぎから仕上げまで一台で完結可能です。
操作方法は包丁を磁石付きベースに固定し、ローラーを前後に転がすだけ。力加減や角度を気にせず、誰でも安定した結果が得られます。天然砥石のように刃を荒らすことなく、プロが狙う刃先を短時間で再現できるのが大きな魅力です。
天然砥石は憧れるけれど扱いが難しそうと感じる方にとって、EDGBLACKはまさに現実的で実用的な選択肢といえるでしょう。
【最高級】天然砥石のおすすめ10選!:まとめ
天然砥石は、日本が誇る伝統的な刃物文化を支えてきました。荒砥・中砥・仕上げ砥と役割を分け、それぞれの産地に特色ある名砥が受け継がれてきました。丹波青砥や伊予砥のように日常の研ぎに使いやすい砥石から、京都・山城合砥や正本山合砥のようにプロが憧れる最高級仕上げ砥まで、その魅力は奥深く、刃物好きなら一度は手にしてみたい存在でしょう。
しかし同時に、天然砥石には「高額になりやすい」「角度や力加減の習得が難しい」「平面出しなどのメンテナンスが必要」といったハードルがあることも事実。包丁研ぎに初めて挑戦する方にとっては、やや敷居が高いと感じるかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、砥石の精度とシャープナーの手軽さを融合させた EDGBLACK Knife Sharpener です。刃を固定してローラーを転がすだけで、誰でも短時間でプロ級の切れ味を再現可能。天然砥石に憧れながらも扱いに不安を感じる方にとって、現実的かつ実用的な解決策といえるでしょう。
ぜひ本記事を参考に、自分に合った研ぎスタイルを見つけてください。天然砥石の奥深さを楽しみたい方も、手軽に切れ味を取り戻したい方も、あなたに最適な一本は必ずあるはずです。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /








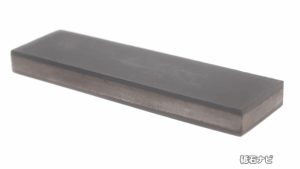

コメント