【簡単】包丁のサビ取りは激落ちくんでいける?100均で買えるアルミホイルや消しゴムは使える?

「包丁にサビが出てきたけど、わざわざ高い研磨剤や専門道具を買うのは面倒…」
「激落ちくんや100均のアルミホイル、サビ取り消しゴムで落とせないかな..?」
と悩む人は多いでしょう。
軽いサビなら家庭にあるアイテムだけで簡単に落とせるケースもありますが、使い方やサビの程度によって効果は大きく異なります。
また、正しい方法を知らずにこすると、刃を傷つけてしまうリスクもあるため注意が必要です。
そこで今回は「激落ちくんで包丁のサビは落とせるのか?100均のアルミホイルやサビ取り消しゴムは効果があるのか?」を徹底解説します。
本記事では、それぞれの特徴や使い方、注意点まで詳しく紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
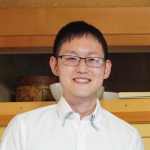
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

包丁のサビ取りは激落ちくんでいける?
結論、包丁のサビ取りに「激落ちくん(メラミンスポンジ)」を使うことは、軽度なサビであれば有効な方法です。
メラミンスポンジは、非常に細かい硬質の樹脂構造を持ち、微細な研磨作用によって表面の汚れや酸化膜を削ぎ落とす性質があります。そのため、目立たないレベルの点サビや表面の酸化であれば、水を含ませて軽くこするだけで除去できる可能性が高いですね。
実際、SNSでも包丁のサビ取りに激落ちくんを活用している方がちらほら見受けられます。
クレンザーと激落ちくんでサビと汚れを大まかに落とした
ばーちゃん愛用の杉本の牛刀。普段は築地のお店に研ぎに出してるけど、今回は事情があって自分で研ぐことに。とりあえずクレンザーと激落ちくんでサビと汚れを大まかに落としたところ。
— やまーだぁ (@ksyr_bike_food) November 7, 2022
観察してみると、表面に和包丁のような切刃があり、その先に少し大きめの糸刃が付けられている様子。
#包丁研ぎ pic.twitter.com/mdEPVqZpej
ばーちゃん愛用の杉本の牛刀。普段は築地のお店に研ぎに出してるけど、今回は事情があって自分で研ぐことに。とりあえずクレンザーと激落ちくんでサビと汚れを大まかに落としたところ。観察してみると、表面に和包丁のような切刃があり、その先に少し大きめの糸刃が付けられている様子。
茶色いサビが激落ちくんで綺麗になってなお嬉しい
あとこれ本当は包丁にはよくないかもだけど、刃の辺りが茶色くなっててサビ?と思ってたのも、激落ちくん(ドイツの白い消しゴムみたいなやつ)で綺麗になってなお嬉しい。
— kyoko (@kyokobb) July 9, 2015
あとこれ本当は包丁にはよくないかもだけど、刃の辺りが茶色くなっててサビ?と思ってたのも、激落ちくん(ドイツの白い消しゴムみたいなやつ)で綺麗になってなお嬉しい。
水と重曹と激落ちくんで少し擦ったら元に戻った
滅多に使わない牛刀を久々に出したら錆のようなものが付いててパニック。ネットで調べたとおりに水と重曹と激落ちくんで少し擦ったら元に戻った!!
— 秋桜子 (@cosmoscsmskko) June 10, 2023
實光刃物の包丁3種使ってるけど、よく切れるお気に入りたちなので少しでも長く使いたい。
滅多に使わない牛刀を久々に出したら錆のようなものが付いててパニック。ネットで調べたとおりに水と重曹と激落ちくんで少し擦ったら元に戻った!!實光刃物の包丁3種使ってるけど、よく切れるお気に入りたちなので少しでも長く使いたい。
ただ、深く進行したサビや刃の根本に広がった腐食には効果がイマイチ。
メラミンスポンジが研磨剤としては非常に「穏やか」な性質を持つためで、表面の汚れには効いても、内部まで進行したサビを完全に落とす力はありません。
また、強くこすりすぎると、刃の表面に細かい傷が入って光沢を損なう原因になるため、優しく力を入れすぎないように磨くのが基本です。鏡面仕上げの包丁や高級ステンレス製の刃物では、研磨跡が目立ちやすくなるので注意しましょう。
包丁のサビ取りは100均で買えるアルミホイルや消しゴムでもいける?
結論から言うと、軽い点サビなら100均のアルミホイルやサビ取り消しゴムで十分に落とせます。
アルミホイルは丸めて水で湿らせ、サビ斑点をやさしく擦るだけでも効果が出ます。
アルミはモース硬度がおよそ2〜2.9と柔らかく、鉄系やステンレス(鉄のモース硬度目安4.5)より軟らかいため、深い傷を入れにくいのがメリットですね。
包丁のサビがケチャップとアルミホイルで取れた
本当にシンクと包丁のサビがケチャップとアルミホイルで取れた!最高!ありがとうインターネット!!!
— ミィ@ぱないの (@grinnirg) December 13, 2019
本当にシンクと包丁のサビがケチャップとアルミホイルで取れた!最高!ありがとうインターネット!!!
包丁の表面の汚れや錆は、アルミホイルで磨くとキレイになる
鍛冶屋『包丁の表面の汚れや錆は、アルミホイルで磨くとキレイになりますよ』台所にあるものでこんなにキレイに🤗✨🔪✨ pic.twitter.com/iBFcmuFcf0
— simanto工房 (@simantokoubou) January 18, 2022
鍛冶屋『包丁の表面の汚れや錆は、アルミホイルで磨くとキレイになりますよ』台所にあるものでこんなにキレイに
一方で「サビ取り消しゴム」は研磨剤入りのゴムブロックで、番手(粒度)がある製品も流通しています。
荒目#80や中目#120などは落ちが速い反面、擦り跡が残りやすいため、包丁には細目を選ぶのが無難ですね。
消しゴムでサビ取りしたら大根切ったら断面がツルツルだった
錆だらけの包丁ね。百貨店の研ぎ師にもってたらさ、困難ダメですわ〜w買い換えたほうが良いと思いますお客様!って言われてさ。むかついてさ。サビ取りの消しゴムみたいな奴で錆を1日かけて取り除いて油をつけて保存して布で磨いてを繰り返してさ。大根切ったら断面がツルツルだったのよ
— 狸 (@komoriuta3) April 10, 2017
錆だらけの包丁ね。百貨店の研ぎ師にもってたらさ、困難ダメですわ〜w買い換えたほうが良いと思いますお客様!って言われてさ。むかついてさ。サビ取りの消しゴムみたいな奴で錆を1日かけて取り除いて油をつけて保存して布で磨いてを繰り返してさ。大根切ったら断面がツルツルだったのよ
消しゴム使えば包丁の軽い錆ならイチコロ
しごおわ
— かたおじ (@kataojisan0220) October 12, 2020
今日は時間あったので僕の商売道具のメンテしてあげました
切れる包丁はやっぱりいいですね
食材の切り口が全く違うし切る音が全然違う
この消しゴムみたいのオススメ
包丁の軽い錆ならイチコロ pic.twitter.com/nToawXc80H
しごおわ。今日は時間あったので僕の商売道具のメンテしてあげました。切れる包丁はやっぱりいいですね。食材の切り口が全く違うし切る音が全然違う。この消しゴムみたいのオススメ。包丁の軽い錆ならイチコロ
まとめると、アルミホイルは「低硬度ゆえに傷を入れにくい下処理」、サビ取り消しゴムは「粒度を選べばポイント除去に強い仕上げ」という棲み分けが適切です。
>>【簡単】アルミホイルの包丁の研ぎ方!切れない包丁の切れ味を復活させる裏ワザ

【100均で完結】錆びた包丁をピカピカにする方法
包丁のサビ落としは「表面の酸化被膜を丁寧に取り除く工程」と「再発を防ぐ仕上げ」の二段構えです。
間違った方法でゴシゴシ擦ってしまうと、サビは落ちても刃が傷ついたり、切れ味が著しく低下する恐れがあります。
軽い点サビなら家庭用の道具だけでも十分対応できますが、深く進行したサビは段階的に処理するのが鉄則です。
次に、錆びた包丁をピカピカにする方法を詳しく解説しますね。
- 中性洗剤で油汚れを落とし、水分をしっかり拭き取る。
- アルミホイルを水で湿らせ、サビ部分をやさしく擦る。
- 消しゴムタイプのサビ取りで、落ちない部分を丁寧にこすり落とす。
- サビが深い場合はクレンザーや専用クリーナーを使って仕上げる。
- 仕上げ後は完全に乾燥させ、薄く油を塗って再発を防ぐ。
順番に見ていきましょう。
ピカピカにする方法①:中性洗剤で油汚れを落とし、水分をしっかり拭き取る
サビ取りはまず下地を整えることから。
包丁の表面には調理中の油や手の皮脂などが付着しており、これが酸化の進行を早める原因になります。なので、市販の食器用中性洗剤を使って刃全体をしっかり洗い、表面の油膜を完全に落としましょう。
特に刃と柄の境目はサビが発生しやすいポイントなので、歯ブラシなどを使って丁寧に洗浄すると効果的です。洗浄後はすぐに柔らかい布で水気を拭き取り、自然乾燥させましょう。
ピカピカにする方法②:アルミホイルを水で湿らせ、サビ部分をやさしく擦る
軽い点サビであれば、研磨剤や薬品を使わずに落とせるケースが多いです。
最も手軽な方法が、アルミホイル磨きです。アルミホイルを2〜3cm程度の大きさに丸め、水で湿らせてからサビの部分を優しく円を描くように擦ります。
アルミの硬度は包丁のステンレスよりも柔らかいため、金属表面を傷つけずに酸化被膜だけを削り落とすことが可能です。強く押し付けすぎると細かい傷がつくため、力加減は“鉛筆で文字を書く程度”が目安です。
擦ったあとは水で洗い流し、布でしっかり拭き取って再度乾燥させておきましょう。小さな点サビならこの段階でほとんど落とせます。
ピカピカにする方法③:消しゴムタイプのサビ取りで、落ちない部分を丁寧にこすり落とす
アルミホイルだけでは落ちないしつこいサビは、100円ショップなどでも手に入る「サビ取り消しゴム」を使うと効果的です。
消しゴムタイプは内部に微細な研磨剤が含まれており、金属表面を削りながらサビを除去します。使用時は角をサビ部分に軽く当て、力を入れすぎずに擦るのがポイントです。
広範囲を一気にこすろうとせず、斑点ごとに丁寧に処理すると刃全体の均一性を保てます。刃先などデリケートな部分は研磨しすぎると切れ味を損なう可能性があるため、必要に応じてマスキングテープで保護してから作業を行うと安心です。
ピカピカにする方法④:サビが深い場合はクレンザーや専用クリーナーを使って仕上げる
サビが点ではなく面として広がっている場合、家庭用のクレンザーや金属専用クリーナーを併用すると効果的です。
クリームタイプのクレンザーを柔らかい布やスポンジに少量取り、刃の流れに沿って直線的に動かします。このとき、円を描くように動かすと研磨ムラが出やすくなるため注意が必要です。
数分ほど優しく磨いたら、水で洗い流して残留物を完全に除去します。さらに深刻な黒サビや食い込みがある場合は、ステンレス用のジェル状クリーナーを使い、数分間置いてから拭き取ると化学的にサビを分解できます。
ただ、長時間放置すると金属表面まで溶かす危険があるため、使用時間は必ず製品の指示を守りましょう。
ピカピカにする方法⑤:仕上げ後は完全に乾燥させ、薄く油を塗って再発を防ぐ
サビ取り作業が終わったら、最後に必ず防錆処理を行います。
流水で洗浄して残った研磨粉や薬剤を完全に洗い流し、布で水分を拭き取ってから風通しの良い場所でしっかり乾燥させましょう。その後、食品にも使える流動パラフィン(ミネラルオイル)や椿油などを薄く塗布します。
金属表面に油膜を作ることで空気や水分との接触を防ぎ、再び酸化が進行するのを抑えるためです。保管場所は湿度が低く、直射日光の当たらない場所が理想的です。
使用後も同様に、毎回の洗浄・乾燥・油膜保護を習慣化することで、包丁の輝きと切れ味を長く維持できますよ。
>>【5選】切れない包丁を切れるようにするには?初心者でも簡単に包丁を研ぐ方法を徹底解説

包丁はサビ取り+定期的に研ぐ必要もある
包丁の性能を長く維持するには、サビを落とすだけで終わらせてはいけません。
表面の酸化を除去した後も、定期的な研ぎによって刃先の状態を整えること必須。サビを取っても、刃先が摩耗して鈍っていれば本来の切れ味は戻らず、使い勝手も大きく損なわれます。
包丁は使うたびに、まな板との摩擦や食材の繊維との接触で少しずつ刃先が丸くなります。目に見えないほどの変化であっても、積み重なれば切れ味が落ち、余計な力が必要になり、手元が滑ってケガをするリスクも高まります。
研ぎのタイミングは、使用頻度によって異なりますが、家庭用なら2〜3か月に一度を目安です。
また、研ぐという行為には「サビ取りでは届かない部分を整える」という役割もあります。サビ取りで落とせるのは表面の酸化だけですが、内部まで侵食していた場合は刃自体を削って再生させる必要があります。
このように、サビ取りと研ぎは別々の作業ではなく、互いを補完し合うものです。
>>【比較】100均のおすすめ包丁研ぎ3社!セリア・ダイソー・キャンドゥの砥石を徹底比較

【簡単】包丁のサビ取りは激落ちくんでいける?:まとめ
包丁のサビ取りは専門の研磨剤や道具を使わなくても、家庭にある「激落ちくん」で手軽に行うことが可能。
メラミンスポンジの微細な研磨作用によって、軽い点サビやくすみ程度なら水だけでこすり落とすことができ、刃を傷つけにくいのも安心できるポイントでしょう。
ただ、深く食い込んだサビや黒ずみには専用のクリーナーや研磨剤との併用が必要です。
加えて、定期的な研ぎも忘れずに対応するようにしましょう。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /










コメント