【簡単】アルミホイルの包丁の研ぎ方!切れない包丁の切れ味を復活させる裏ワザ

「包丁の切れ味が落ちて料理の効率が悪くなったけれど、砥石を使うのは難しそうで面倒…」
そんな悩みを抱える方は多いです。
専用の研ぎ器を持っていない場合、簡単に試せる方法がないか探している人も多いでしょう。
そこで今回は「簡単にできるアルミホイルの包丁の研ぎ方」を徹底解説します。
本記事では、家庭で誰でもできる裏ワザ的な方法を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
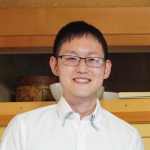
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

【簡単】アルミホイルの包丁の研ぎ方
包丁の切れ味が落ちたときに、砥石が手元になくても手軽に試せる方法として注目されているのがアルミホイルを使った研ぎ方です。
専門的な知識や特別な器具を必要とせず、家庭にあるもので簡単に切れ味を改善できるのが特徴。
まずは具体的な手順を解説していきます。
- アルミホイルを30cmほど切り取り、数枚重ねて折りたたむ
- 包丁の刃をアルミホイルに差し込み、根元から刃先まで引くように切る動作をする
- この動作を10回程度繰り返す
- 使用後は刃に付着したアルミ片を水で洗い流し、布でしっかり拭き取る
- 最後に試し切りをして切れ味を確認する
順番に見ていきましょう。
アルミホイルの包丁の研ぎ方①:アルミホイルを切り取り折りたたむ
市販されている一般的なホイルを30cm程度切り取り、何度か折りたたんで厚みを持たせましょう。
4〜6回程度折ると程よい強度になり、刃先をあてても破れにくく作業しやすくなります。この折りたたむ工程を省略すると刃がすぐに突き抜けてしまい、思うように効果を得られないので注意してください。
家庭用ホイルの厚さは通常10〜15ミクロンほどであり、そのままでは柔らかいため、重ねることで摩擦力を高める狙いがあります。
アルミホイルの包丁の研ぎ方②:刃を差し込み根元から刃先まで動かす
準備したアルミホイルに包丁を差し込み、根元から刃先までを滑らせるように切る動作を行います。
このときのポイントは、往復ではなく一方向に引くことです。往復させると刃の当たり方にムラが生じ、効果が均一にならない場合があります。
切るといっても力を入れる必要はなく、ホイルを軽く裂くような感覚で構いません。この摩擦によってホイルの微細な金属片が刃の細かな傷に入り込み、表面をなめらかに整える働きが期待できます。
刃をまんべんなく当てることを意識して、全体を均一に動かすことが重要です。
アルミホイルの包丁の研ぎ方③:適切な角度を意識して操作する
包丁をホイルに当てる角度も切れ味改善のために大切です。
包丁によりけりですが、一般的には刃を15〜20度ほど傾けて動かすと効果的です。角度が浅すぎると刃先に十分な摩擦が生じず、深すぎると逆に削りすぎてしまう恐れがあります。
そのため、やや寝かせた角度を保ちながら均一に滑らせるのが理想です。調理中に野菜を切る際の角度を思い出しながら作業すると感覚をつかみやすいでしょう。
アルミホイルの包丁の研ぎ方④:同じ動作を10回程度繰り返す
刃先全体に均一な効果を与えるためには、同じ動作を複数回繰り返すことが必要です。
目安は10回程度。包丁の状態に応じて回数を増減させます。新品に近い包丁であれば少ない回数で十分ですが、明らかに切れ味が落ちていると感じる場合は15回程度まで行っても問題ありません。
ただ、過度に繰り返すと刃を傷めることにつながるため、あくまで軽度の調整として行うことを心がけましょう。切れ味の改善が体感できるかどうかは、実際に食材を切って確認するのが確実です。

アルミホイルの包丁の研ぎ方⑤:洗浄と試し切りで仕上げる
研ぎ終わった包丁にはアルミ片や細かな削りかすが付着しているため、必ず水で洗い流す必要があります。
その後は布巾やペーパーでしっかり拭き取り、水分を残さないように乾燥させます。乾燥が不十分だとサビの原因になるため、仕上げは丁寧に行うことが大切です。
最後にトマトや玉ねぎなどの柔らかい食材を切ってみると、切れ味が改善しているかを簡単に確認できますよ。
とはいえ、あくまで応急的な方法であるため、長期的には砥石を使った本格的な研ぎ直しと併用するとより安定した切れ味を維持できます。

アルミホイルで包丁を研ぐデメリット
アルミホイルで包丁を研ぐのは簡単な一方で、下記のようなデメリットがあるのも認識しておきましょう。
- 刃こぼれや傷がつきやすく、包丁を痛める可能性がある
- アルミホイルは柔らかいため、十分に研げず切れ味が改善しにくい
- 不均一に摩耗し、刃先がかえってガタつく場合がある
順番に見ていきましょう。
デメリット①:刃こぼれや傷がつきやすく、包丁を痛める可能性がある
アルミホイルは柔らかく、研磨材として十分な硬度を持っていません。
そのため刃に均等な圧力がかからず、摩擦が局所的に強くなることがあります。この過程で刃先に小さな傷がついたり、既にある刃こぼれが悪化したりするケースがあるわけです。
包丁の刃先は非常に繊細で、均一な力と正しい角度で研ぐことが重要です。しかしアルミホイルではその条件を満たせず、意図せず刃を痛めてしまう危険が高いのです。
デメリット②:アルミホイルは柔らかいため、十分に研げず切れ味が改善しにくい
包丁を研ぐためには、鋼材よりも硬度の高い研磨材で刃先を削り、角度を整える必要があります。
しかし、アルミホイルは包丁の鋼材に比べてはるかに柔らかいため、理想的な研磨効果を得ることはできません。折りたたんで厚みを出しても、刃を鋭く整えるには力不足であり、表面的な摩擦で「多少ましになった」と錯覚する程度。
そのため切れ味の改善が持続することはなく、数回の使用で再び鈍さを感じるケースがほとんどです。本格的な砥石やシャープナーで得られるような鋭さは再現できないため、あくまで応急的な処置と割り切るしかありません。
デメリット③:不均一に摩耗し、刃先がかえってガタつく場合がある
アルミホイルを用いた研ぎ方は、刃全体を均一に削ることが難しい点が問題です。
摩擦のかかり方にムラが出るため、刃先の一部は削れすぎ、別の部分はほとんど削れないといった状態になりがち。その結果、刃先のラインが乱れてガタつきが生じ、切る際に引っかかりや抵抗を感じることがあります。
さらに、この不均一な摩耗が続くと、刃先の角度が崩れて調理のたびに余計な力が必要となり、食材を滑らかに切ることが難しくなります。きちんと整えられた刃先と比べて切断面も荒くなり、料理の見た目や食感にまで影響が出る可能性があります。

しかし、砥石は難易度が高く、シャープナーは簡単だが効果はイマイチ
砥石は正しい角度を維持して研ぐ技術が必要で、初心者には難易度が高いと言われます。角度がずれると刃が均一に削れず、かえって切れ味を落とす原因になるため、習得には時間と経験が求められます。
一方、スロットに差し込むだけのシャープナーは手軽に扱えるのが利点ですが、実際には刃先を荒らすことで一時的な切れ味を作っているにすぎません。そのため効果の持続性は短く、数回の使用で再び切れ味が落ちてしまいます。
そこでおすすめなのが「EDGBLACK」です。
従来の砥石に比べて圧倒的に扱いやすい構造が特徴です。角度は包丁の種類に合わせて適正角度を固定できる仕組みになっています。
また、粗研ぎから仕上げまでを一台で完結させられます。研ぎ方は角度を設定し、砥石を装着して前後に転がすだけの簡単な工程で、片面につきおよそ30秒から1分程度で十分な研磨が可能です。
砥石は難しい、シャープナーは物足りないという場合は、両者の長所を併せ持ったEDGBLACKが最適でしょう。
【簡単】アルミホイルの包丁の研ぎ方:まとめ
- アルミホイルを30cmほど切り取り、数枚重ねて折りたたむ
- 包丁の刃をアルミホイルに差し込み、根元から刃先まで引くように切る動作をする
- この動作を10回程度繰り返す
- 使用後は刃に付着したアルミ片を水で洗い流し、布でしっかり拭き取る
- 最後に試し切りをして切れ味を確認する
アルミホイルを使った包丁の研ぎ方は、応急的に切れ味を回復させる方法としては手軽ですが、長期的に見ると刃を痛めたり均一に研げなかったりするデメリットがあります。
そのため普段使いの包丁を大切にしたい方には、本格的に刃先を整えられる専用の研ぎ器を選ぶことが賢明です。
「EDGBLACK」であれば、従来の砥石のように難しい技術を必要とせず、シャープナーのように簡単に使える構造を持ちながらも、本格的な研磨効果を得られる点が強みです。粗研ぎから仕上げまで一台で対応できるため、日常の料理で常に安定した切れ味を維持できます。
アルミホイルの方法はあくまで一時的な裏技と割り切り、長期的には信頼できる道具を使うことが包丁を長持ちさせる最良の方法です。
安心して切れ味を維持したい方には、EDGBLACKを活用するのが最も合理的な方法と言えるでしょう。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /









コメント