【危険?】包丁にシャープナーはダメ?メリット・デメリットを徹底解説

シャープナーは、一定の角度で刃先を削って短時間で切れ味を整えることができる優れもの。
しかし、シャープナーは手軽な一方で、「使うと刃が傷む」「寿命が短くなる」といった声もあり、本当に使っていいのか迷う方も多いはず。
そこで今回は「包丁にシャープナーはダメなのか?」をメリット・デメリットの観点より徹底解説します。
本記事では、シャープナーの具体的な事例を交えて紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
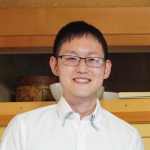
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

包丁にシャープナーはダメ?
包丁にシャープナーはダメなのか?
結論から言うと、実際には状況により使い分ける方が適切です。
例えば、和包丁や片刃包丁にシャープナーを使うと、刃の角度が崩れて切れ味や刃持ちが低下するリスクがあります。
というのも、一般家庭では平砥石での研ぎ直しは月に1~2回が目安とされるのに対し、簡易シャープナーを使うなら週に1度の頻度が必要になるというメーカーもあるからです。
とはいえ、シャープナーは短時間で切れ味を一時的に回復させるという意味では有効な補助手段。忙しい日常でほんの少し切れ味を復活させたい場面には便利ですが、刃角や刃先の維持を重視するなら、角度を保てる砥石研ぎを主体にしつつ、シャープナーは補助として軽く短回数で用いるのが賢明です。
要するに、シャープナーを全面否定するのではなく、用途や包丁の種類に応じた適切な使い分けこそが、切れ味と刃の寿命を両立させるポイントになると言えるでしょう。
>>【比較】砥石とシャープナーの違いは?7項目からどっちがいいのかを徹底比較

包丁をシャープナーで研ぐメリット
では、次に包丁をシャープナーで研ぐメリットを解説していきますね。
- 短時間で切れ味を回復できる
- 専門知識や技術が不要
- 均一な角度で研げる
- コンパクトで保管しやすい
- 低コストで導入できる
順番に見ていきましょう。
メリット①:短時間で切れ味を回復できる
電動式シャープナーでは、粗研ぎ・中研ぎ・仕上げの3工程をすべて行っても90秒から120秒程度で完了するモデルもあります。
砥石を使った場合、平均して10〜15分ほど必要になることを考えると、時間効率は約5〜8倍に相当。短時間で済むため、調理中に刃の引っかかりを感じても、ほとんど中断せずに作業を再開できるのが大きなメリットです。
研ぎの時間を短縮することで手首や前腕への負担が軽減され、長時間の料理作業でも疲労が溜まりにくくなるのもメリットと言えるでしょう。
メリット②:専門知識や高度な技術が不要
固定角度ガイドを搭載したシャープナーは、15度や20度など、包丁に最適な角度で自動的に研磨できる設計になっています。
これにより、砥石研ぎで必要となる刃の当て方や圧力の加減を習得する必要がなくなります。例えば、あるモデルでは刃を溝に差し込み、軽く数回引くだけで研ぎが完了します。
操作が単純でミスが少ないため、初心者でも購入初日から安定した切れ味を得られます。砥石の場合、均一な角度を保ちながら研ぐには数時間の練習が必要ですが、シャープナーなら練習なしで同等の結果を得られることが多いです。
メリット③:均一な角度で研げる
固定角度式シャープナーの中には、研ぎ角度の誤差を±1度以内に抑える精密設計を持つ製品もあります。
この精度は手研ぎでは難しく、特に初心者の場合は角度のばらつきによって刃先の摩耗が不均一になりやすいです。均一な角度で研がれた刃は、切れ味が長持ちし、切断面が整いやすくなります。
食材に対する抵抗が減少するため、野菜の薄切りや肉の筋切りなど、精度を求められる調理でもスムーズな作業が可能です。また、左右対称に刃を研ぐことで、包丁のバランスが崩れにくく、長期間安定した使用感を保てます。
メリット④:コンパクトで保管しやすい
手動式シャープナーは全長10〜12センチ、幅5〜6センチ、重量200〜300グラム程度の小型軽量設計が主流です。
キッチンの引き出しや収納棚に簡単に収まり、取り出しやすい形状が多く採用されています。電動式でも卓上ミキサーほどの設置面積で、作業台に置きっぱなしにしても邪魔になりません。
こうした省スペース性は、使用頻度を高める重要な要素。必要な時にすぐ取り出して使える環境が整えば、刃のメンテナンスを後回しにすることが減り、結果として切れ味を維持する機会が増えます。
さらに、軽量で持ち運びが容易なため、アウトドアや出張料理の現場にも対応可能です。
メリット⑤:低コストで導入できる
手動式シャープナーの価格帯は1,000〜3,000円程度、電動式でも5,000〜8,000円で高性能モデルを入手可能です。
これに対し、プロの研ぎサービスは1回あたり1,000〜2,000円が相場であり、年に数回利用すればシャープナーの購入費をすぐに回収できます。
一度購入すれば数年単位で使用できるため、長期的には大きなコスト削減。特に家庭で複数本の包丁を所有している場合、経済的メリットはさらに大きくなりますね。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

包丁をシャープナーで研ぐデメリット
逆に、包丁をシャープナーで研ぐことは、以下のようなデメリットも存在します。
- 刃の寿命が短くなる
- 角度が合わない場合がある
- 刃先が欠けやすくなる
- 片刃包丁には不向き
- 研ぎ残しが出やすい
順番に見ていきましょう。
デメリット①:刃の寿命が短くなる
多くの簡易シャープナーは研磨力が強く、1回の使用で0.05〜0.1ミリ程度の金属を削り取ることがあります。
これは砥石での手研ぎよりも削除量が多く、長期的には刃の厚みが早く減少します。刃先が薄くなると耐久性が低下し、欠けや曲がりが起こりやすくなるため、結果として包丁自体の寿命が短縮します。
特にステンレスや硬度の高い鋼材では、過剰な研削が刃の性質を損なう原因に。頻繁に使用する場合は、削る量が少ない低研磨モデルやホーニングロッドとの併用が望ましいでしょう。
デメリット②:角度が合わない場合がある
シャープナーは固定角度で設計されており、多くは15度や20度に設定されています。
しかし、日本の和包丁は片側15〜16度、洋包丁は片側20度前後と異なるため、角度が合わないまま研ぐと刃先が鈍くなったり不自然な形状になります。角度の不一致は切れ味だけでなく、食材への入り込みや耐久性にも影響します。
刃物メーカーの推奨角度を確認し、それに対応するシャープナーを選ばなければ、本来の性能を引き出すことは困難です。とはいえ、角度調整機能付きのモデルを選ぶことで、この問題は軽減できますね。
デメリット③:刃先が欠けやすくなる
研磨力が強すぎるシャープナーや粗目の研磨ホイールは、刃先に過剰な負荷をかける場合があります。
特に硬度の高い鋼材では、一部に応力が集中し、マイクロチップと呼ばれる微細な欠けが発生しやすくなります。欠けは切断時の抵抗を増やし、さらに刃こぼれが進行する要因となります。
加えて、粗目の研磨材は刃先の表面を荒らすため、錆の発生リスクも高まります。刃先の欠けを防ぐには、粒度の細かい仕上げ工程を持つモデルを使用することが重要です。
デメリット④:片刃包丁には不向き
和包丁に多い片刃構造は、片面だけに特定の角度で研ぎを入れる必要があります。
一般的なシャープナーは両刃構造を前提としており、片刃を通すと反対側の不要な部分まで削ってしまいます。この結果、刃線が変形し、切れ味や食材の切断面に悪影響を与えます。
寿司包丁や出刃包丁など、精密な切断を求められる包丁では、シャープナーの使用は相性が悪いです。こうした包丁は砥石による片刃専用の研ぎ方でメンテナンスする必要があります。
デメリット⑤:研ぎ残しが出やすい
固定式シャープナーは刃全体を均等に研ぐ構造ですが、刃の形状や長さが異なると、先端や根元まで研磨が届かないことがあります。
この研ぎ残し部分が切れ味のムラを生み、実際の使用感に不均一さをもたらします。特に刃元付近は構造上スロットに入りにくく、研ぎ残しが発生しやすい箇所です。
とはいえ、使用後に刃先全体を確認し、不足部分を補助的に砥石やホーニングロッドで整える方法である程度は補填可能です。
シャープナー向きの包丁
シャープナーに向く包丁は、刃の形状や材質がシャープナーの設計角度や研磨方式と合致しているものです。
もっとも適しているのは両刃の洋包丁。洋包丁は多くが片側20度前後に仕上げられており、市販されているシャープナーの多くも15度から20度で設計されているため、角度が一致しやすく効率的な研ぎが可能になります。
三徳包丁もシャープナー向き。三徳包丁は日本と西洋の特徴を融合した形状で、多くが両刃仕様となっており、角度も洋包丁に近い16〜20度の範囲に収まります。この角度は固定式シャープナーの設計範囲に適合しやすく、刃先を均一に研ぐことができます。
ステンレス製の包丁もシャープナーでの研ぎに適しています。ステンレスは錆びにくく、研磨時の摩擦熱や削り粉に対する耐性が高いため、シャープナーによる研磨において刃の損耗を最小限に抑えることができます。また、ステンレスの硬度は一般的にHRC54〜58程度で、シャープナーの研磨材(セラミックやダイヤモンド砥粒)でも効率よく刃先を整えられる硬さです。
シャープナー向きではない包丁
シャープナー向きではない包丁は、刃の構造や素材の特性が固定角度や溝型の研磨方式と合わないものです。
代表的な例として片刃包丁。片面だけに刃をつける構造は、両側同時に削るシャープナーを通すと反対側の不要な部分まで研磨され、刃線が変形します。柳刃や出刃などの和包丁は特に精密な切れ味と形状を保つ必要があるので、こうした包丁は角度や当て方を調整できる砥石での研ぎが適しています。
また、セラミック製の包丁も向きません。セラミックは硬度が非常に高く、一般的な金属用シャープナーでは十分な研削ができず、逆に欠けを発生させる危険があります。チタンコーティング包丁の場合も、研磨中にコーティング層が削り落とされ、防錆や切離れの性能が低下します。
さらに、波刃やパン切り包丁のようなギザギザ形状の刃は、シャープナーの直線的なスロットでは形状に沿った研磨ができず、刃の山や谷の一部しか削れません。その結果、切れ味が均一に戻らないだけでなく、形状そのものが崩れる恐れがあります。
包丁にシャープナーはダメ?:まとめ
包丁にシャープナーを使うことは一概に避けるべきではなく、正しく選び、適切に使用すれば十分に有効です。
確かに角度の不一致や過剰な研削による刃の寿命短縮といった注意点はありますが、固定角度式や粒度の細かい仕上げ機能を備えたモデルを選べば、切れ味を保ちながら長く使えます。
特に日々の料理で手軽にメンテナンスを行いたい方にとって、短時間で結果が得られるシャープナーは非常に便利な存在です。砥石研ぎが難しい初心者や、忙しくて研ぎの時間が確保できない場合でも、安定した切れ味を維持できます。
選び方と使い方を誤らなければ、シャープナーは包丁を快適に保つための頼れる相棒となるでしょう。
また、シャープナーのように手軽に使えて砥石の効果を期待できるEDGBLACKのようなハイブリッド型の商品もあります。詳細は下記よりご覧ください。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /









コメント