【難しい】薄刃包丁/和包丁の研ぎ方!片刃包丁はシャープナーより砥石を使うべき?

薄刃包丁の研ぎ方が分からず、切れ味が落ちたまま放置していませんか?
薄刃包丁や和包丁は片刃構造のため、洋包丁とは研ぎ方が大きく異なります。特に初心者の方の中には、「シャープナーで研いでもいいの?」「砥石を使うのは難しそう…」と悩むケースも少なくありません。
結論から言えば、薄刃包丁の研ぎには砥石を使うのが基本。正しい手順とポイントさえ押さえれば、初めてでも切れ味をしっかり取り戻すことができます。
この記事では、薄刃包丁の特徴と片刃ならではの研ぎ方、シャープナーとの違い、初心者が失敗しやすい注意点までを分かりやすく解説します。自宅でも安心して研げるようになりたい方は、是非参考にしてください。
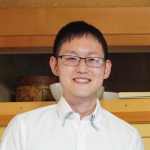
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

薄刃包丁/和包丁の定義
薄刃包丁(うすばぼうちょう)とは、主に野菜の下ごしらえや細工に特化した片刃の和包丁で、刃先がまっすぐで薄い形状を持つことが最大の特徴。
柳刃包丁や出刃包丁と並んで和包丁を代表する存在であり、特に関東型薄刃包丁が一般的に薄刃包丁と呼ばれることが多いです。
関東型薄刃包丁は、刃渡りが家庭用では180mm前後、プロ用では210〜240mm程度が主流。刃の形状は直線型で、柳刃包丁のような反りがなく、野菜をまっすぐに切る作業に適しています。刃元から刃先にかけて非常に薄く仕上げられているため、食材への抵抗を最小限に抑え、滑らかな切れ味を実現します。
また、構造上の大きな特徴は片刃であることです。右利き用の場合は右側が鋭角に研がれ、左側は裏すきと呼ばれる緩やかな凹みを持つ平面になっています。この裏すきによって、食材が刃に張り付きにくく、また研ぎやすさや切れ味の安定性にもつながっています。
用途は、野菜の桂剥き、面取り、飾り切りなど、繊細で真っすぐな切断面が求められる場面です。薄刃包丁は刃が薄く硬いため、肉や骨を切る用途には不向きですが、野菜を美しく仕上げるためには欠かせない一本と言えます。
他の和包丁との違い
薄刃包丁について、代表的な他の和包丁とのすみ分けを表形式で分かりやすくまとめたものが以下の通りです。
| 包丁の種類 | 刃の形状・構造 | 主な用途 | 特徴・メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 柳刃包丁 | 長く、先端が細く反っている/片刃 | 刺身・魚の切り身 | 引いて切ることで刺身など滑らかに切れる。和食の盛り付けに最適。 | 肉や野菜の汎用には不向き。刃渡りが長く扱いに慣れが必要。 |
| 出刃包丁 | 厚く重みがある刃/片刃が主流 | 魚の下ろし・骨を断つ作業 | 骨や硬い部分も力強く切れる。刃が丈夫で衝撃に強い。 | 重量があり細かい作業には向かない。野菜には不適。 |
| 薄刃包丁 | 薄くまっすぐな直線刃/片刃(裏すきあり) | 野菜の桂剥き、面取り、飾り切り | 野菜を繊細かつ美しく仕上げられる。真っすぐな断面が作りやすい | 刃が薄く硬いため、骨・冷凍食品などを切ると刃こぼれの恐れあり。扱いにはコツが必要。 |
ご覧の通り、一口に和包丁と言っても明確な違いがあるのです。
補足:鎌薄刃との違い
正確に言えば薄刃包丁には、関東型と関西型の2種類があります。関西でよく使われる鎌薄刃包丁は、刃先が鎌のように丸く反っているのが特徴で、野菜の細工切りや皮むきなど、曲線的な動きを活かす作業に適しています。
一方、関東型薄刃包丁は刃先がまっすぐな直線型で、桂剥きや真っすぐな切断面を作る作業に特化。見た目の形状だけでなく、用途や包丁の動かし方も異なり、同じ薄刃という名称でも役割は明確に分かれています。
【切れ味最強】恐ろしく切れる包丁!切れ味ランキングTop.7を紹介します

砥石を用いた薄刃包丁の正しい研ぎ方
薄刃包丁は、菜切り包丁や洋包丁とは異なり、片刃構造を持つため独自の研ぎ方が必要です。刃の片面だけが鋭角に研がれ、裏面には「裏すき」と呼ばれる凹みがあるため、角度や手順を誤ると切れ味が落ちるだけでなく、刃の形を崩してしまう恐れも。
正しい研ぎ方を身につければ、家庭でもプロと同じような鋭い切れ味を保つことが可能です。基本は、砥石を使って一定の角度で表側を丁寧に研ぎ、裏面でバリ(かえり)を取って仕上げる流れとなります。
研ぎに使う道具と準備:砥石の番手目安など
薄刃包丁を正しく研ぐには、適切な砥石と安定した作業環境が欠かせません。まず砥石は、基本研ぎには#1000〜#2000程度の中砥石、仕上げには#3000以上の仕上げ砥石を用意するのが一般的。
ちなみに包丁の切れ味を戻すだけであれば中砥石だけでも十分対応できます。作業前には砥石をしっかり水に浸し、気泡が出なくなるまで吸水させることで、研ぎ面を滑らかに保ちやすくなります。
さらに重要なのが、砥石をしっかり固定することです。滑り止め付きの台を使用したり、濡れ布巾を敷いて安定させましょう。
砥石の表面は使ううちに中央がへこみやすいため、定期的に面直し砥石や平らな板で平面を整えることも大切です。砥石が歪んでいると研ぎ角度がブレやすく、均一に刃がつかなくなるため、研ぎの精度に大きく影響します。
薄刃包丁(片刃包丁)の研ぎ方手順
薄刃包丁は片刃構造のため、研ぎ方は「表 → 裏 → 仕上げ」の3ステップで行うのが基本です。以下工程ごとに丁寧に進めることで、切れ味が均一になり、刃の持ちも良くなるはず。
- 表側を研ぐ(刃のついている面)
- 裏側を軽く研ぐ(裏すき面)
- 仕上げとバリ取り
まず表側は、砥石に対して包丁を10〜15度ほど傾け、刃元から刃先まで均等に研ぎ進めます。角度を安定させることが何より重要です。
続いて裏側は、裏すきと呼ばれる緩やかな凹みを意識しながら、表で出たバリ(かえり)を優しく取り除くイメージで研ぎます。
最後に表と裏を交互に数回ずつ研ぎ、刃先全体を均一に整えれば完了。仕上げ後は水洗いして砥石の粉を落とし、しっかりと乾燥させるように意識しましょう。
初心者が失敗しやすいポイント
薄刃包丁の研ぎは、角度や力加減、裏面の扱いなどに独特のコツがあり、慣れないうちは思わぬ失敗をしやすいものです。研ぎ方の基本を押さえていても、ちょっとした手順のズレが切れ味や刃の形に大きく影響してしまいます。
特に初心者にありがちな失敗しやすいポイントが以下の通り。
- 角度が安定せず、刃先が丸まってしまう
- 裏面の研ぎが不十分でバリが残る
- 砥石の面直しを怠って歪んだまま研いでしまう
片刃包丁では、10〜15度程度の角度を常に一定に保つことが何より重要。角度がブレると刃先が丸まり、せっかく研いでも切れ味が鈍くなってしまいます。
また、裏面を軽視するとバリが残り、切り込みが悪くなるだけでなく、切断面が荒れる原因になります。さらに、砥石の平面が崩れた状態で研ぐと角度が一定にならず、刃がいびつになってしまうことも。
これらは初心者がつまずきやすいポイントですが、逆に言えばここを丁寧に押さえるだけで研ぎの精度は格段に上がります。
ちなみに、包丁研ぎの頻度についてですが必ずしも多ければ多いほどいいというわけではありません。用途や目的に合った最適な頻度があるのです。詳細は以下記事にて解説していますのでご参考下さい。
【月1?】包丁研ぎの頻度は?包丁を砥石で研ぐ頻度はどのくらいがベスト?

片刃包丁はシャープナーより砥石を使うべき?
薄刃包丁のような片刃包丁は、構造上シャープナーでは正しく研ぐことができません。市販のシャープナーは、両刃包丁(洋包丁や菜切り包丁)向けに設計されており、左右対称の刃付けを行う仕組みになっているためです。
繰り返しになりますが片刃包丁は、表面が鋭角に研がれ、裏面に裏すきと呼ばれる凹みを持つ特殊な構造を持ちます。なので、シャープナーを使うと刃の角度が崩れたり、裏面に不均一な摩耗が生じ、かえって切れ味が落ちる原因になりかねません。
砥石を使えば、表と裏をそれぞれ適切な角度・力加減で研げるため、片刃包丁本来の鋭い切れ味を長く維持できます。また、刃先の状態を自分でコントロールできるので、刃こぼれや摩耗にも柔軟に対応可能。
最初は少し手間に感じるかもしれませんが、長い目で見れば砥石での研ぎが最も確実で包丁を長持ちさせる方法と言えるでしょう。
【砥石】菜切り包丁の研ぎ方は間違えやすい?片刃/両刃タイプによる角度の違いを解説

薄刃包丁で両刃タイプのものも存在
薄刃包丁といえば片刃構造が基本ですが、近年では家庭用向けに両刃タイプの薄刃包丁も登場しています。これは、従来の片刃のような専門的な研ぎ方を必要とせず、洋包丁と同じ感覚で扱えることが特徴。
両刃の薄刃包丁は、左右対称に刃がついているため、まっすぐ切りやすく、左利きの人でも使いやすいのが大きなメリットです。また、特に気を付けずに研ぎも砥石で両面を均等に研げばよく、初心者でも比較的メンテナンスが簡単です。
両刃構造であれば市販のシャープナーを使った研ぎも幾分か可能となってきます。勿論、より精密に仕上げたい場合は砥石を使った方が理想的ですが、日常的な簡易メンテナンスとしては十分実用的と言えるでしょう。
今日、プロ仕様の繊細な切れ味には劣るものの、日常的な野菜のカットには十分な性能を持った両刃タイプの薄刃包丁は市場に多く出回っています。
シャープナーと砥石、どちらを使うべきなのかについて知りたい方は以下の記事をお読みすることもおすすめいたします。
【危険?】包丁にシャープナーはダメ?メリット・デメリットを徹底解説

面直しや角度調整の手間を省けるEDGBLACKという選択肢
薄刃包丁をしっかり研ぐには、砥石の番手選びや角度の維持、面直しなど、正しい手順を踏む必要があります。しかし、初心者にとってこれらはなかなかハードルが高いのも事実。そんな悩みを解消してくれるのが、我々EDGBLACKブランドの最先端研ぎ器です。
EDGBLACKは砥石の特性とシャープナーの手軽さを組み合わせた構造で、片刃包丁にも対応できる精密な角度調整機能を備えています。専用の砥石プレートは安定性が高く、砥石の平面を保ちながら均一に研ぐことが可能。面直しの手間もほとんどなく、理想的な研ぎ角をキープしやすい設計仕様となっています。
砥石の扱いは難しそうと感じていた人でも、EDGBLACKを使えば短時間で安定した切れ味を再現でき、薄刃包丁の性能を最大限に引き出せます。初心者から中級者まで、自宅で本格的な包丁研ぎを実現したい人におすすめのアイテムですよ。
【難しい】薄刃包丁/和包丁の研ぎ方:まとめ
薄刃包丁は、野菜を繊細かつ美しく仕上げるために欠かせない和包丁ですが、その性能を最大限に活かすには正しい研ぎ方が重要です。基本的には片刃構造を持つため、研ぎは「表 → 裏 → 仕上げ」の3ステップを丁寧に行う必要があり、角度の安定やバリ取り、砥石の平面管理などが切れ味を大きく左右します。
両刃タイプの薄刃包丁であればシャープナーも活用可能ですが、片刃タイプの場合は砥石による手研ぎが最も確実で長持ちする方法と言えるでしょう。
また、近年では両刃タイプや初心者向けモデルも増えており、あくまで自分の使い方やレベルに合わせて道具を選ぶことも大切。研ぎの難しさを感じる場合には、我々のEDGBLACKのように角度調整機能や安定性を備えた高精度なシャープニングシステムを活用するのも一つの選択肢でしょう。
正しい研ぎ方と適切な道具を組み合わせれば、自宅でも薄刃包丁特有の鋭い切れ味を長く保つことができます。まずは基本を押さえ、少しずつ慣れていくことが上達への近道です。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /










コメント