【包丁研ぎ方】砥石番手の最適な順番は?おすすめの組み合わせまで徹底解説!

包丁を研ぐときに欠かせない砥石。しかし、#400・#1000・#3000といった番手の違いや、どの順番で使うのが正解なのか、迷う人も多いのではないでしょうか。
砥石の番手は数字が小さいほど荒く、大きいほど仕上げ向きですが、単に「粗 → 中 → 仕上げ」と並べれば良いわけではありません。包丁の状態や素材、研ぎの目的によって、最適な組み合わせは変わります。
この記事では、包丁を効率よく、かつ理想の切れ味に仕上げるための砥石番手の選び方と順番を分かりやすく解説します。初心者でも迷わず実践できるよう、用途別のおすすめパターンや組み合わせ例も紹介するので是非最後までご覧ください。
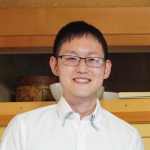
サカイ販促サポート株式会社 代表取締役。砥石ブランド「EDGBLACK」の日本総代理店を務める。EDGBLACKブランドでのクラウドファンディング総支援額は5,300万円超。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /

【基礎知識】砥石の番手とは?
包丁を研ぐときに欠かせない砥石ですが、番手と呼ばれる数字の意味を正しく理解している人は意外と少ないものです。
番手は、砥石の粒の細かさを示す指標であり、包丁の切れ味を左右する大切な要素。適切な番手を選べていないと、刃がうまく研げなかったり、かえって傷つけてしまうこともあります。
まずは、この番手がどのような基準で決められ、研ぎの仕上がりにどんな影響を与えるのかを簡単に確認していきましょう。
番手ごとの役割と特徴
繰り返しになりますが、砥石は大きく「荒砥石」「中砥石」「仕上げ砥石」の3種類に分かれます。まず荒砥石(#200〜#600程度)は、欠けた刃を修復したり、刃先の形を整える段階で使用。削り量が多く、刃の形状を短時間で修正できる反面、使い方を誤ると刃を削りすぎることもあるため注意が必要です。
次に中砥石(#800〜#2000前後)は、最も汎用性が高く、日常的なメンテナンスに最適。荒研ぎでついたキズを整え、滑らかな切れ味を取り戻します。
最後の仕上げ砥石(#3000〜#8000以上)は、鏡面のような刃先をつくる仕上げ工程に使用します。研磨粒が非常に細かいため、包丁の切断抵抗を減らし、スッと吸い込むような切れ味を実現します。
これ以外にも砥石には、素材や形状等によっても細かく種類が分かれています。また、表記がなく、番手が正確に判別しにくいことも。それらも含めて砥石の種類に関する詳細は以下別記事も参考にしてみて下さいね。
【粗さ】砥石の種類5選!番手がわからない時の対処法まで徹底解説

【目的別】砥石番手のおすすめの組み合わせ
それでは今回のメインテーマである、研ぎたい包丁の状態や目的別に合わせた、おすすめの砥石番手の組みあわせについて解説していきます。
主に以下3つの目的ごとに、砥石番手の組み合わせを考えることをおすすめします。
- 刃こぼれを直したい場合
- 日常メンテナンスで切れ味を保ちたい場合
- 和包丁など鋭い切れ味を求める場合
それぞれ詳しく確認していきましょう。
刃こぼれを直したい場合のおすすめ組み合わせ:#400前後→#1000程度→#3000〜#4000
包丁の刃こぼれや欠けがある場合は、まず低番手の荒砥石(#400前後)からスタートするのが基本。荒砥石は研磨力が高く、刃先の欠けや丸まりを短時間で整えられます。ただし削りすぎには注意が必要で、刃の形状を確認しながら少しずつ研ぐのがコツ。
次に中砥石(#1000程度)を使い、荒研ぎでできた細かい傷を取りながら、刃線をなめらかに整えます。この段階で刃の直線性や均一な角度を意識すると、仕上げが格段に美しくなります。
最後に仕上げ砥石(#3000〜#4000程度)で刃先を磨くことで、研ぎ跡が消え、切り始めの抵抗が減少します。
つまり、#400 → #1000 → #3000の3ステップが、欠け修復と切れ味復活の黄金パターン。刃のダメージが大きい場合ほど、低番手から丁寧に段階を踏むことが重要です。
日常メンテナンスで切れ味を保ちたい場合:#1000前後→#3000程度
日々の料理で使用する包丁は、刃こぼれがなくても次第に切れ味が鈍くなっていきます。このような軽度の切れ味低下を整えるなら、中砥石(#1000前後)を中心としたシンプルな研ぎ方が最適。
まず#1000で刃先全体を均一に研ぎ、刃の微細な摩耗や巻きを取り除きます。強く押し当てすぎず、刃全体をやさしく滑らせるように研ぐのがポイント。その後、#3000程度の仕上げ砥石を軽く当てることで、滑らかな刃面と鋭い切れ味が復活します。
この「#1000 → #3000」の2段構成は、最もバランスが良く、初心者にもおすすめの基本セットです。
頻繁に研ぐ必要はなく、月に1回ほどのメンテナンスで十分。研ぎすぎによる刃の摩耗を防ぎながら、包丁本来の性能を長期間維持できます。まさに“無理なく続けられるメンテナンス研ぎ”といえるでしょう。
和包丁など鋭い切れ味を求める場合:#400〜#600→#1000〜#2000→#6000〜#8000
刺身包丁や柳刃包丁など、繊細な切れ味を追求する和包丁を研ぐ場合は、より高番手の砥石を組み合わせるのが理想です。
まず荒砥石(#400〜#600)で刃形を整え、不要な歪みや欠けを修正します。次に中砥石(#1000〜#2000)で刃先を安定させ、荒研ぎで残った粗い傷を丁寧に除去。
ここからが本番で、#6000〜#8000の仕上げ砥石を使うことで、刃先が鏡面のように光り、紙やトマトの皮をスッと切れる鋭さに仕上がります。
高番手は粒度が極めて細かく、摩擦熱が上がりやすいため、研ぎの際は水を多めに含ませて滑らせるのがコツです。
また、片刃包丁の場合は裏面を軽く裏押しして平面を整えると、食材への食い込みがさらに滑らかになります。
この工程により、包丁の性能を最大限に引き出し、職人のような吸い付く切れ味が蘇ります。
【方法】包丁の切れ味を確認するには?新聞紙/ティッシュ/食材/爪など利用可!

砥石を使う順番と注意点
砥石を使う基本の順番は、「荒砥石 → 中砥石 → 仕上げ砥石」。この流れを踏むことで、刃の形を整えつつ段階的に研磨が細かくなり、最終的に理想的な切れ味を得られます。荒砥石(#400前後)で欠けを修正し、中砥石(#1000前後)で刃先を均一に整え、仕上げ砥石(#3000以上)で刃面を磨き上げるのが基本です。
ただし、「毎回全ての工程を行う必要があるのか?」という疑問を持つ人も多いでしょう。結論から言えば、包丁の状態に応じて一部の工程を省略しても問題ありません。例えば、刃こぼれがない場合は荒砥石を使わず、「#1000 → #3000」の2工程でも十分に切れ味を取り戻せます。
逆に、刃が大きく欠けているときに中砥石や仕上げ砥石だけを使っても効果は薄く、荒砥石から段階的に進める必要があります。
また、どの工程でも角度を一定に保つことが大切です。両刃包丁なら15〜20°、片刃包丁なら10°前後を意識しましょう。さらに、砥石の平面を保つ・水を十分に含ませる・力を入れすぎないといった基本も忘れてはいけません。
つまり、順番はあくまで基本形であり、状態に応じて柔軟に調整するのが包丁を上手の研ぐ秘訣というわけです。
砥石を全て揃えると費用はどのくらい?
荒砥石・中砥石・仕上げ砥石をすべて揃えるとなると、意外に費用がかかるものです。
一般的な家庭用の人工砥石でも、荒砥石が2,000〜3,000円前後、中砥石が3,000〜5,000円、仕上げ砥石が5,000〜8,000円ほどが相場。合計で1万円を超えることも珍しくありません。さらに、砥石を平らに保つための「面直し砥石」や「砥石台」などを追加すると、総額は1万5,000円を超えることもあります。
勿論、長期的に見れば砥石を揃えることで包丁の買い替え頻度を減らせるため、結果的にコスト削減になる側面もあります。ただ、初心者にとっては「どれを買えばいいかわからない」「全部そろえるのは高い」と感じるのも自然なことです。
そのため、最初のうちは中砥石(#1000前後)だけを購入して練習するのも十分に現実的な選択です。中砥石はメンテナンスにも汎用的に使え、研ぎの感覚をつかむのにも適しています。
慣れてきた段階で、必要に応じて荒砥や仕上げ砥を追加していく方法だと無理がありませんよ。
天然砥石の場合は番手の考え方が違う?
天然砥石には、人工砥石のような明確な番手の基準はありません。
人工砥石はJIS規格によって研磨粒の大きさが数値化されており、「#400」「#1000」などの数字で粒度を判断できます。
一方、天然砥石は採掘された鉱脈や地層によって粒の細かさや成分が異なるため、同じ採石場でも一枚ごとに研ぎ味が違うのが特徴です。
そのため、天然砥石では「#何番相当」といった数値よりも、感触や仕上がり具合で分類されます。例えば、粗めで硬い石は荒砥、中程度の削れ方なら中砥、滑らかで艶の出る石は仕上げ砥といった具合です。
また、天然砥石の研磨粒は角が丸く、刃にやさしく当たるため、番手換算では#6000〜#10000相当でも、実際の仕上がりはそれ以上に滑らかに感じることもあります。
要するに天然砥石は、数値よりも研ぎ感で選ぶのが正解となります。上記の内容も含めて天然砥石と人工砥石の違いや考え方についての詳細は以下記事も参考にしてみて下さい。
【5選】天然砥石の見分け方!人造砥石との違いやメリット・デメリットまで徹底解説

初心者でもプロ級の仕上がりを実現できる新しい砥石 ― EDGBLACK
砥石を揃えて正しい順番で研ぐのは理想的ですが、実際には「角度が安定しない」「番手を揃えると高くつく」「仕上げの差が出にくい」と悩む人も多いでしょう。
そんな課題を解決するのが、我々のEDGBLACKシャープナーシリーズです。
EDGBLACKは、初心者でも一定の角度をキープしながら研げる構造を採用。独自のガイド機構と高品質な砥石ユニット(#400/#800のダイヤモンド面、または#1000セラミック面)によって、正しい番手順をワンタッチで再現できます。
従来の砥石のように3種類を買い揃える必要がなく、1台で粗研ぎから仕上げまでをカバー。角度ブレを防ぎつつ、滑らかな刃先を安定的に仕上げられます。
まさに、砥石に慣れていなくてもこれ一つでプロ級の切れ味を実現できる次世代型の研ぎツールです。包丁研ぎの常識を変えるEDGBLACKの使い心地を、是非一度体感してみてください。
【包丁研ぎ方】砥石番手の最適な順番は:まとめ
包丁を研ぐうえで、砥石の番手や使う順番を理解することは欠かせません。荒砥石で刃を整え、中砥石で均一に研ぎ、仕上げ砥石で磨くという基本を守ることで、刃こぼれのない理想的な状態に近づけます。
ただし、包丁の状態によっては中砥石だけでも十分な場合があり、無理にすべての工程を行う必要はありません。
また、砥石をすべて揃えるには一定のコストがかかるため、初心者にとってはハードルが高いのも現実です。
そんな中で注目されているのが、我々のEDGBLACKのように正しい角度と番手順を一台で再現できるシャープナー。
砥石の知識がなくても、誰でも手軽にプロ級の研ぎが実現でき、包丁の切れ味と寿命を同時に伸ばせます。
まずは自分の包丁の状態に合わせた研ぎ方を見極め、正しい順序とツールを選ぶことから始めましょう。
\ シャープナーのように使える革命的な砥石 /










コメント